�@
|
������w
�@�u���̂��鑍����w����������w�̂悤�ȏ����ȑ�w�ɓ��w�������v�Ƃ������Z��������ƕ����B�܂��A�u�������苳�炵�Ă��炦���w�v�Ƃ��đ�����w�������鍂�Z���������Ȃ��Ȃ��ƕ����B������w�̋��������Â��铱������u���Ȕ����v�u���𒆐S�ɁA������w��FD��T�����B
|

����@�� �o�c���w����
|
 |
�Θb���镶����FD��g�߂ɂ���
|
�@FD�̐�i�I�ȑ�w�̈�Ƃ���鑽����w�A���̋���Ƃ͂����Ȃ���̂��B�傢�Ȃ鋻���Ɗ��҂������āA�u������w�ł͂ǂ̂悤�ȃv���Z�X���o��FD�������w�g�D�Ƃ��Ď��{�ł���悤�ɂȂ������v�ɂ��Đq�˂��B�Ƃ��낪�A���o�c���w�����̓����́A�u������܂��̑�w�ɂȂ낤�ƐS���������ʂł��v�ƁA���q��������قǃV���v���������B
�@�����āA���́u������܂��̑�w�Â���v�Ƃ������O�̒��S�ɂ���̂��A�w����̂̋��炾�Ƃ����B�u���X�������Ă����w���ɍ��킹�āA������˂ɕω����Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�����āA���̕ω����鋳����x���Ă���̂��A�����Ɗw���̑Θb�̕����Ȃ̂ł��v�ƍ���w�����͌����B
�@���́u�Θb�̕����v���w���ŌJ��L������ꏊ���������E���W���B�����ŋ����������̎��ƕ]���̌��ʂ𑼂̋����Ɍ��\���A�c�_��������A�w�������ƃf�B�X�J�b�V����������i�����풃�ю����Ƃ����B
�@�܂�A������w�́AFD���w�S�̂ōs�����߂̑g�D�����邩��@�\���Ă���̂ł͂Ȃ��A���Ƃ��Ƒ�w�Â���̒i�K����u�w���Ɏ��_�����킹������@�ցv�Ƃ��Ă̑f�n�����݂��Ă������߂Ɏ��R��FD���@�\���Ă����Ƃ����悤�B
|
 |
�A�h�o�C�U�[���x���s�K�v�ȑ�w
|
�@�ߔN�A�w���Ƃ̃R�~���j�P�[�V������[�߂鐧�x�Ƃ��āA�ǂ̑�w�ł������������͌�������Ă���̂��A�h�o�C�U�[���x�ł���B�������A������w�ł͊J�w�������������x�����Ă������̂́A���݂͔p�~���Ă���B���̗��R�ɂ��āA����w�����́u�w���͂ǂ̋����Ƃ����ڂɃR�~���j�P�[�V�������Ă���̂ŁA�����̋����S�ɉ����āA�K�X���ɋ�����I��ő��k�ɍs���܂��B���̂��߁A����̋����ɃA�h�o�C�U�[�ɂȂ��Ă��炤���Ǝ��́A�Ӗ����Ȃ��̂ł��v�ƌ����B
�@����́A���K�͑�w�Ȃ�ł͂̋����Ɗw���Ƃ̊W�Ƃ����悤�B�����Ɗw�����R�~���j�P�[�V������[�߂邽�߂̕��@�̓A�h�o�C�U�[���x�Ɍ���Ȃ����Ƃ��킩��B�ꍇ�ɂ���ẮA���w���Ɍ��߂���A�h�o�C�U�[�Ƃ��肪���킸�ɑ�w���������W�Ɖ߂����w��������ƕ����B
�@������w�̂߂��������Ɗw���̊W�́A���݂����e�����Ȃ邽�߂̂��̂ł͂Ȃ��B�ނ���u�w�����������Ȃ���w�K���A�[��������w�������߂������߂̂��́v�Ƃ����悤�B
|
 |
�\���I�Ȋw�K�̎p���Ɓu���̂̍l�����v���w��
|
�@�w�����������ƂŌ��C���Ȃ��A�g�ɂȂ��Ă���������ɉ��P���邩���ǂ̑�w�ł��؎��Ȗ��ɂȂ��Ă���B������w�ł͂�������P���邽�߂ɁA2002�N�x�J���L�������Ɂu���Ȕ����v�u���Ƃ���1�N���K�C�Ȗڂ荞�B���̉Ȗڂ͒��J�ފw������̃R�[�f�B�l�[�g�̂��ƁA5�A6�l�̐�C�������S������B
�@����́A�u�w�Ԃ��Ǝ��̂��ړI�v�Ƃ������Ƃɍ��Z���ォ�犵�炳��Ă����w���ɁA�w�Ԃ��߂̐V�������@�����Ă��炤���Ƃ��_�����Ƃ����B���̂��߁A���܂܂ł̋����v�l�g��j���āu���̂��߂Ɏ����͊w�Ԃ̂��v�����H�I�ɔ��������@���Ƃ��Ă���B�u���Ȕ����v�u���̃V���o�X������Ɓu�t�B�[���h���[�N�v�Ɓu�m���邽�߂̒m���Ƃ�����w�m�̋Z�@�x��g�ɂ���w�K�v�̑傫����̕�������\������Ă���B
�@�t�B�[���h���[�N�ł�10�l���x�̊w���O���[�v���A�u�`�̂Ȃ����ԑт�y�j���Ȃǂ𗘗p���Ēn���E�����s���ӂ�����āA�n��Љ�̂������邳�܂��܂ȉۑ�i�������j������B�����āA���̉ۑ�����P���邽�߂̃A�C�f�A���o���A�v��̗��Ă��s���B�ۑ�����P���邽�߂̃A�C�f�A���o���Čv�悷��͔̂�r�I���₷���B�������A��������ۂɒn��Љ�Ɏ���Ă��炤�悤�ɋ�̉����邱�Ƃ́A�����ȒP�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�Ⴆ�ΐ��x��̐���₳�܂��܂ȎЉ��A���Q�W����̉���j�ށB�����ŕK�v�ɂȂ�̂��A�ۑ�ɑ���Љ�I�w�i�ւ̎���̊g��ƁA�����Ɍ����Ă̔��z�̓]�����B
�@�����Ď��̃X�e�b�v�Ƃ��āA�ǂ̃v�����������I���A�O���[�v���ł̃f�B�X�J�b�V������֘A����m���̎��W���s���B����ɁA�v����s�����ւ̒�Ăɂ܂Ƃ߂Ē�o���A�v���[���e�[�V�������s���B���̎��Ƃŋ����͊w���̊w�K�������`�F�b�N���A�x�����闧��ɓO����B�܂����m�����K�v�ȏꍇ�ɂ͂��̉ۑ�ɓK�����������A�h�o�C�X���s���B
�@���N7���̊w�����ɂ́A�t�B�[���h���[�N�̍ŏI���\���s����B02�N�x�́A�u���ǂ��o�X�^�s��ڎw���āv�Ƃ������s�����`�[�����D�������B���̓��e�́A�����s�����ǂ�������o�X��ʂɖ����ł��邩���l���A�u�S�ݓX�ł̔������ȂǁA���ړI�Ɏg����o�X�J�[�h�E�V�X�e���v�u��q���g�����Ȃ݂��`�F�b�N�ł���悤�ȋ��̐ݒu�v�Ȃǂ̒�Ăɂ܂Ƃ߂����̂��B�����̒�Ă̈�͑����A�n���o�X��Ђ������Ɍ����Č��������Ƃ����B���́u���Ȕ����v�u���ɂ���āA�w�K���@������Ɠ����ɖ��̔����`�T���`�����Ƃ����w�Ԏ�@���A�w���ɐg�ɕt���Ă����B
|
 |
2�N�Ԃقږ������т�p��V�����[
|
�@�����ЂƂ��j�[�N�ȋ����������Ƃ���A�uEnglish Shower�v���B��w�Ƃ������̂́A�{���V�����[�𗁂т�悤�Ɍ��t���A�b���Ă����Ȃ��ŁA���R�Ɛg�ɕt�����̂��Ƃ����l��������A�u�p��V�����[�v�Ɩ��Â��Ă���B���ꂩ��̃r�W�l�X��S���l�ނɂƂ��āA�p��ɂ��R�~���j�P�[�V�����\�͂��������Ȃ��Ƃ����ϓ_����݂���ꂽ���Ƃ��B���̎��{���@�́A������w�炵���O�ꂵ�Ă���B
�@���w������2�N�Ԃ����ăR�~���j�P�[�V�����̊�b�\�͂���n�܂�A�o�c���Ɋւ�����I�ȗp��܂ł킩���Ęb���郌�x���܂ʼnp��͂����߂邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B�O�ꂵ�Ă���̂́A�T4�����邱�̎��Ƃ͂��ׂ�1���Ԗڂ���ݒ肳��Ă��邱�Ƃ��B�u������\������R�~���j�P�[�V�����̗͂�g�ɕt�����i�Ƃ��Ė����A���ł���������p��ŕ\�����邱�Ƃ���Ȃ̂ł��v�ƍ���w�����͌����B
|
 |
�����̌��͂��̂܂܂Ɋw���̖����x���グ��
|
�@������w�̃J���L�������̔������x�̓[�~�i�[���`���̎��Ƃ��Ƃ����B�����ɂƂ��āA���Ƃő����̊w����O�ɂ��Đ��m�����������͔̂�r�I�e�Ղ��B�܂��A���₪�o�Ă��A��̗\�z�ł���͈͓��Ȃ̂ŁA�˘f�����Ƃ����Ȃ��B�������f�B�X�J�b�V�������������[�~�i�[���`���ɂȂ�ƁA�����̃R�[�f�B�l�[�g�\�͂������B���邢�͗\�z�O�̎������m���ȊO�̂��Ƃ���ւ̑Ώ������߂��A���Ɖ^�c�͓���B�܂��āu���Ȕ����v�u���̂悤�ɁA�w���Ɍʂ̃e�[�}�̖����A�T���A����������ƂȂ�ƁA�����̋����̓f�B�X�J�b�V�����̐i�ߕ��Ɏn�܂��āA���\�̂������Ɏ���܂Ō˘f�����Ƃ������B���̏ꍇ�A���Ɖ^�c�����ȋ�����ΏۂɁA���C���s�����Ƃ��l������B�������A������w�̂����́A��������Ă���B���F�A���������̓w�͂ł͌��E������ƍ���w�����͎w�E���A�ߋ��̎��s������Љ���B
�@������w���J�w�����́A���Ɖ^�c�����ʓI�ɍs�����߂ɁA�����S���Ƀp�\�R�������^�A���Ƃ������g�������łȂ��A�v���[���e�[�V�����\�t�g�����ʓI�Ɏg���Ď�����d�q�t�@�C���Ŋw���ɒł���悤�ɂ����Ƃ����B���������̌��ʁA�ϋɓI��IT�����p���鋳���Ƃ����ł͂Ȃ������̌l�������܂�ɑ傫�����ƂƁA���p���Ȃ��Ă����Ɖ^�c�͏\���ł��Ă��鋳�������邱�Ƃ����������B
�@���̂��߁A�u�e�����̌������āA������Ƌ��炵�悤�v�Ƃ������ʔF���ɖ߂����̂��Ƃ����BIT����g�������Ƃł��A�����̔M�ӂ�����`���Ȃ���ΈӖ����Ȃ��B������������Ɠ`���邱�Ƃ̕������Ɖ��P�̖{�����B
�@���̈���ŁA�w���ɂ͑S���m�[�g�p�\�R�����ݗ^�����B�\���͂���ʓI�ȃv���[���e�[�V�����́A���ƂŊw�������������[�h���邮�炢�ł����Ă��悢�Ƃ������z�̓]�����B��������ɑ���T�|�[�g�̐������낻���ɂȂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����ɂ�MIC�i���f�B�A�E�C���t�H���[�V�����E�Z���^�[�j���K�v��v�]�ɉ����ċ����@�̎x�����s���BMIC�͏��c�[���ɂ��x���ƂƂ��ɁA�}���قƘA�g���Đ}���E���������̏���x���ɂ��w�߂Ă���B
|
 |
�ǂ���\�����錾�t����������Ȃ�
|
�@������w�̑�w�ē�������Ɓu�ςȑ�w�ł��v�Ƃ����L���b�`�R�s�[���\���������Ă���B����͑�����w�̗ǂ���\������K�Ȍ��t����������Ȃ����Ƃ��t��Ɏ�����A�s�[�����B
�@ �u�]���A��w�ōs���Ă����m���`�B�^�̎��Ƃł���A�]���͊y�ł��v�ƍ���w�����͌����B����ʼnۑ蔭����ۑ�����^�A����������Έӎ��J���^�̎��Ƃ����w���̊w�K���ʂ̋q�ϕ]���͊m������Ă��Ȃ��B�m���Ɋw������́A���ƌ�Ɂu�w�т������ς�����v�u���������ς�����v�u�g�łȂ��A�ϋɓI�ɒn��Љ�����ς������Ǝv����悤�ɂȂ����v�Ƃ������z���o�����B���������̒��x�ł���A�����܂ł��w���̌l�I�ȐS���̕ω��Ƃ����ړx�ɂȂ��Ă��܂��B
�@���̈ӎ��J���^�̋��琬�ʂɑ���]���ɂ��āA����w�����͊O���]���⑲�Ɛ��̏A�E��̊���Ɋ��҂��Ă���B�����������w�����܂��܂ȎG���ō����]���Ă���Ƃ������������邩��ł��낤�B���������A�S��662��w�̊w���ɑ��钩���V���Ђ̃A���P�[�g�����ł́A�u��w���v�Œ��ڂ��Ă����w�v�Ƃ���16�ʁA���{�o�ϐV���Ђ̒����ł́u�����x���`���[�𑽂������Ă����w�v�Ƃ���3�ʂɃ����N���ꂽ�i�������02�N�x�����j�B�O������̕]���̍����͗�R�Ƃ��Ă���B�������A�����̕]�������R�Ȃ̂�������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�J�w�������獂���]����������悤�ȑ�w�Â���ɓO���Ă����̂�����B
|
 |
�u������܂��̑�w�v�̈Ӗ��������
|
�@������w�̏���w���A��c��v�����ݗ����ɖڎw�����̂́A�`���ɂ��G�ꂽ�u���Ԃɒʗp���邠����܂��̑�w�ɂ���v�Ƃ������Ƃ������B���̑�w���́A������@�Ƃ��āu���_�����e�_������H����v�Ƃ������Ƃł������B������w����w���v�̐�i�I����Ƃ��Ē��ڂ����̂��A�e�_�Ƃ��Ă̐��X�̋�̓I�Ȏ��{���e�����邩�炾�B�����̑�w�ɐ�삯�čs��ꂽ�A�w���ɂ����ƕ]����V���o�X�̍쐬�ɂ��w���ւ̔N�Ԏ��ƊT�v�ƃX�P�W���[���̒A���̃X�P�W���[�����v��ʂ�Ɏ��{���閳�x�u�V�X�e���A���ѕs�U�҂ւ̑ފw�������x�A�Y�ƊE����̐ϋɓI�ȋ����̗p�Ȃǂł���B
�@�Y�ƊE����̐ϋɓI�ȋ����̗p�ɂ���āA�Љ�̓��������ƂŃ��A���^�C���ɓ`���邱�Ƃ��ł���B�����̋����ɂ͐����k����ł͂Ȃ��A���s�k�����Ƃ̒��ŏЉ�A���͂��Ă��炤�B���̂��Ƃ��w��������E�C�Â���Ƃ����B
�@����w�����̂����u�Θb���镶���v��A�g�ƒu�������āA�u�Љ�Ƒ�w�i���E���j�A�����Ċw���v�̘A�g�̂悤����}�������Ă݂��i�}�\�j�B���̘A�g�̌��ʁA�w���Ƌ��E���A��w�ƎЉ�Ƃ̑��ݍ�p���������A������w�̋���̃��j�[�N���ɂȂ����Ă���B
|
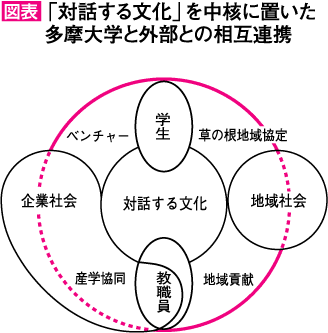
|
 |
�u������Ƌ��炵�悤�v�������t��
|
�@����w������FD���i�̐ӔC�S���҂̗��ꂩ��A����̑�����w�̓W�J�ɂ��āA�uFD���w���̒����ɂ������v�ƍl���Ă���B���̂��߂ɂ́AFD�����Ƃ��Ă̋���ς����ׂĂ̋����ɋ��L����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u������Ƌ��炵�悤�v�Ƃ��������t���A�������E���W�ł̑Θb�ɂ���āu�������畗�y�v�ɂ��悤�Ƃ��Ă���B���Ȃ݂ɁA�����ł̕��y�Ƃ͑�w���L�̕ς��ʏK�����w���B
�@����w�����́A�Љ�l�����̑�w�@������錻�݁A���K�͒P�ȑ�w�Ƃ��Đ��������ꂽ�A��背�x���̍�����w��ڎw�����Ƃ���w�Ƃ��Ă̌�������ɃA�s�[�����邱�ƂɂȂ���Ǝ咣����B�����āA���̂悤�ȃr�W�������u���n�v���O�����v�ƕ\������B
�@�Y�w�A�g�𒅎��ɐi�߁A�w���̑��l�Ȋw�K�s���Ƀ}�b�`�������Ƃ̓W�J��}��Ƃ����J�w����̋���Ɖ^�c�̐����p������邱�ƂŁA����ɍ�������@�ւƂ��ď[�����Ă������Ƃ����҂����B
|
���g�b�v�ւ��ǂ�
����w�E�Z��g�b�v�ւ��ǂ�
���o�b�N�i���o�[ |