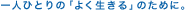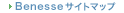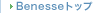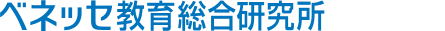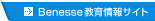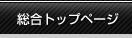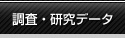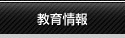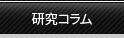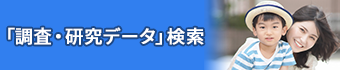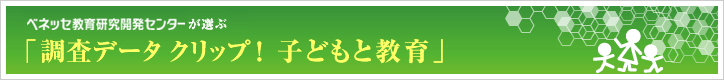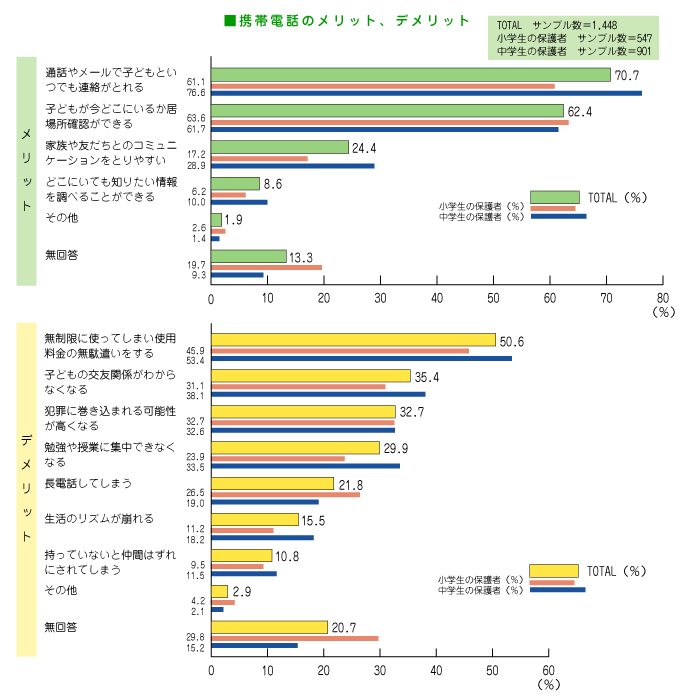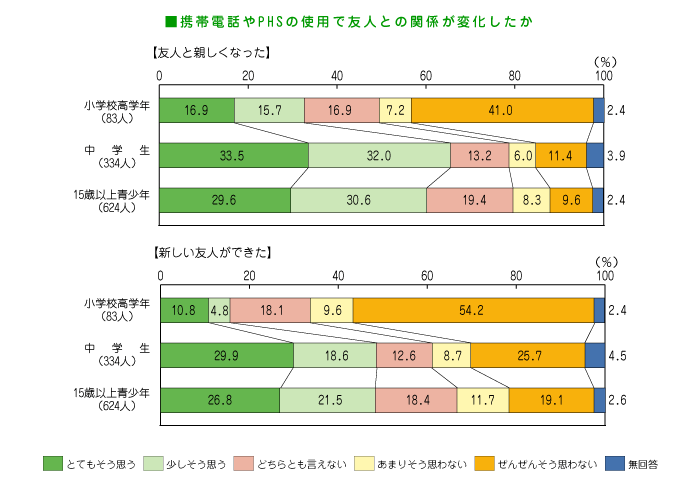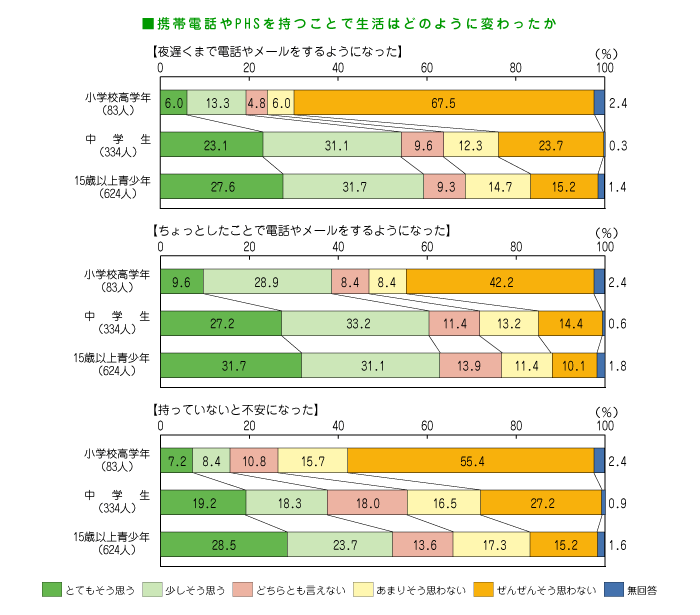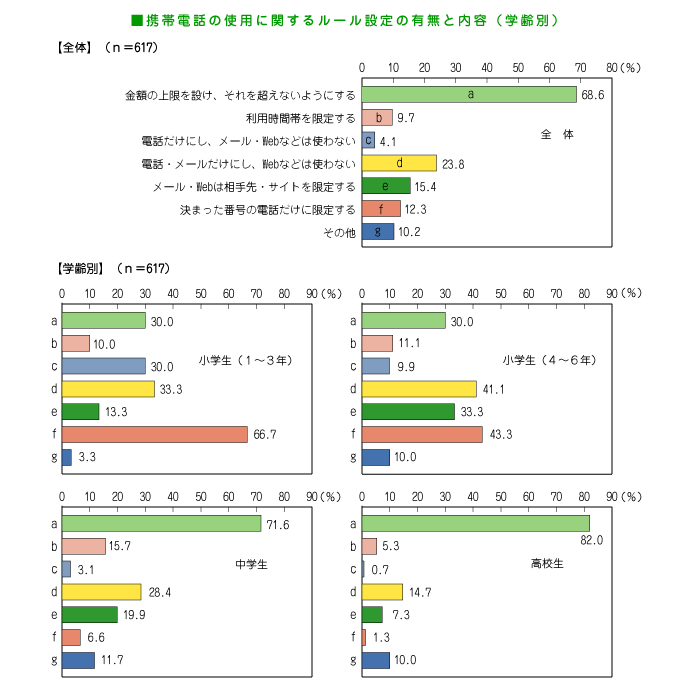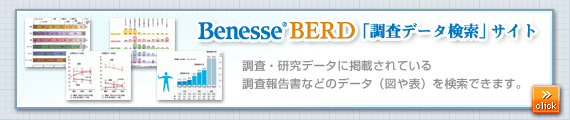�g�ѓd�b�̗��p���� �`��Q��`
|
�y2-1�z�ی�҂�������ő�̃����b�g�́u�q�ǂ��Ƃ��ł��A�����Ƃ��v
- �o�T
- �u�q�ǂ��ƃ��f�B�A�Ɋւ���ӎ��������ʕ��v�i�Ёj���{PTA�S�����c��i2006�j
- �����Ώ�
- ���w5�N���A���w2�N���APTA����i�ی�ҁj ���ی�҉B�g�ѓd�b�EPHS���u�q�ǂ��͎����Ă��Ȃ��v�Ɖ����l�������B
�q�ǂ��̌g�ѓd�b�^PHS�̗��p�ɂ��āA�ی�҂������Ƃ��ǂ��Ǝv���_�́u�ʘb��[���Ŏq�ǂ��Ƃ��ł��A�����Ƃ��v�i70.7���j�ƂȂ��Ă���B�����ő����̂��u�q�ǂ������ǂ��ɂ��邩���ꏊ�m�F���ł���v�i62.4���j�ŁA�e�q���ǂ�ȂƂ��ł��A�����Ƃ��_�ɑ傫�ȃ����b�g�������Ă���悤���B
�S�z�ȓ_�Ƃ��ẮA�u�������Ɏg���Ă��܂��g�p�����̖��ʌ���������v��50.6���Ƃ����Ƃ������A�u�q�ǂ��̌�F�W���킩��Ȃ��Ȃ�v�i35.4���j�A�u�ƍ߂Ɋ������܂��\���������Ȃ�v�i32.7���j�������B�܂��A�u������ƂɏW���ł��Ȃ��Ȃ�v�i29.9���j��u���d�b���Ă��܂��v�i21.8���j�A�u�����̃��Y���������v�i15.5���j�ȂǁA�����K����w�K�ԓx�Ɉ��e�����y�ڂ����Ƃւ̌��O���݂�ꂽ�B
�y2-2�z�F�l�W�ւ̉e���A���w����5�����u�V�����F�l���ł����v
- �o�T
- �u���N���f�B�A���������v���{����������������琬�x�����i2004�j
- �����Ώ�
- ���w���`���N�A����т��̕ی��
- ���g�ѓd�b�E�o�g�r�����L���Ă��鏬�w���`���N
�g�ѓd�b��PHS���g���悤�ɂȂ��Ă���̗F�l�W�ɂ��āA���w���̂R���̂P�i32.6���j�A���w���̂R���̂Q�i65.5���j���u�F�l�Ɛe�����Ȃ����v�Ɠ����Ă���B�܂��A�u�V�����F�l���ł����v�ɂ��ẮA���w����15.6���Ƒ����Ȃ����A���w���ɂȂ��48.5�����u�����v���v�Ɖ��Ă���B�g�ѓd�b���g���悤�ɂȂ��ĉƑ���F�l�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������~���ɂȂ邾���łȂ��A��F�W���̂��̂��L�����Ă�������ɂ��Ȃ�悤���B
�y2-3�z���w���̐����ɕω��������炷�u�P�[�^�C�ˑ��v
- �o�T
- �u���N���f�B�A���������v���{����������������琬�x�����i2004�j
- �����Ώ�
- ���w���`���N�A����т��̕ی��
- ���g�ѓd�b�E�o�g�r�����L���Ă��鏬�w���`���N
�u�g�ѓd�b��PHS�������ƂŐ����͂ǂ̂悤�ɕς�������v�ɂ��āA���w���̉ߔ������u������Ƃ������Ƃœd�b��[��������悤�ɂȂ����v�i60.4���j�A�u��x���܂œd�b��[��������悤�ɂȂ����v�i54.2���j�Ɠ����Ă���i���l�́u�ƂĂ������v���v�Ɓu���������v���v�̍��v�j�B
�u�����Ă��Ȃ��ƕs���ɂȂ����v�́A�u�����v��Ȃ��v�i�u���܂肻���v��Ȃ��v�Ɓu�����v��Ȃ��v�̍��v�^�ȍ~���j��4���ȏア�����A4����́u�����v���i�����Ă��Ȃ��ƕs���ɂȂ����j�v�ƒ��w�������Ă���B�P�[�^�C�Ɉˑ��������Ȑ����𑗂�p���_�Ԍ�����B
�y2-4�z�e�q�̃��[���A���w���͎g�����̐����A�������͋��z����
- �o�T
- �u�u�q�ǂ��̌g�ѓd�b���p�v�Ɋւ��钲���vgoo���T�[�`�z�[���y�[�W���i2006�j
- �����Ώ�
- �ugoo���T�[�`�v�o�^���j�^�[�i�L���Ґ�2,129���j
���q�ǂ�����p����g�ѓd�b��ۗL���Ă���l
�u�u�q�ǂ��̌g�ѓd�b���p�v�Ɋւ��钲���v�igoo���T�[�`�z�[���y�[�W�j�ɂ��ƁA�q�ǂ����g�ѓd�b���g�p����ۂɁA�e�q�ԂłȂ�炩�̃��[����ݒ肵�Ă���l��6���i58.4���j����B
�@���[���̓��e�ɂ��ẮA�u���z�̏����݂��A������Ȃ��悤�ɂ���v��68.6%�Ƃ����Ƃ������B
���[���̓��e���w��ʂɂ݂�ƁA��1���`��3���̕ی�҂ł����Ƃ������̂́u���܂����ԍ��̓d�b�����Ɍ��肷��v��3����2�i66.7���j�̐l�������Ă���B�w�N���オ���ď�4���`��6���̕ی�҂ɂȂ�ƁA�u���܂����ԍ��̓d�b�����Ɍ��肷��v�i43.3���j�Ɓu�d�b�E���[�������ɂ��AWeb�Ȃǂ͎g��Ȃ��v�i41.1���j�������Ƃ������B
���w�E���Z���̕ی�҂͌X�������Ă���A�u���z�̏����݂��A������Ȃ��悤�ɂ���v��7�A8���ɒB����B�ی�҂́A�q�ǂ������w���̂����͘A���ł��鑊��悪�L����Ȃ��悤�ɋC��z��A���w���ȏ�ɂȂ�Ɠ��e�̐��������A���z�̏����ݒ肵�ė}����悤�ɋC�������Ă���悤���B
- �Q�l����
- �u�q�ǂ��ƃ��f�B�A�Ɋւ���ӎ������������ʕ��v�i�Ёj���{PTA�S�����c��
- ���N���f�B�A�����������{����������������琬�x����
- �u�u�q�ǂ��̌g�ѓd�b���p�v�Ɋւ��钲���vgoo���T�[�`
- �u���o�C���Љ��2006�v���o�C���Љ����