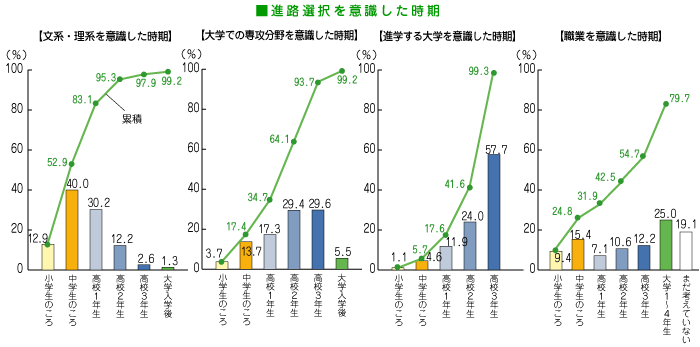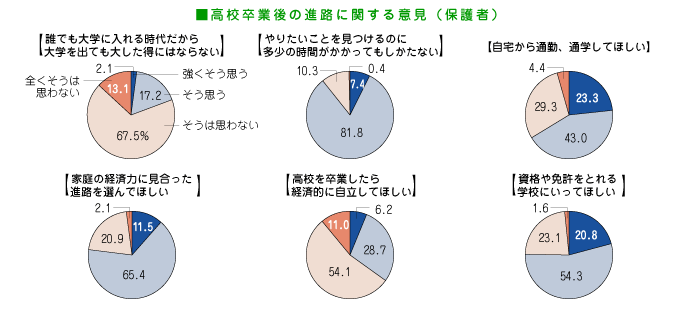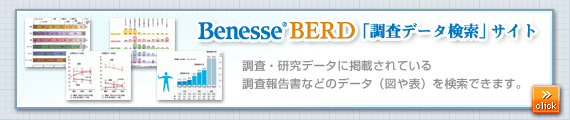�i�H�I���E�L�����A���� �`��P��`
|
�y1-1�z��w�E�Z��ւ̐i�w�����ߔ������A�j�����Ȃ��Ȃ�
- �o�T
- �u����18�N�x�� �����Ȋw�����v�����Ȋw�ȁi2006�j�^�u����19�N�x�w�Z��{��������v�����Ȋw�ȁi2007�j
- �����Ώ�
- �S��
��w�E�Z��ւ̓��w�Ґ��̐��ڂ��݂�ƁA�����S�N���s�[�N��18�ΐl�����������Ă���ɂ�������炸�A��w�E�Z��ւ̓��w�Ґ��̍��v�ɂ���قǑ傫�Ȍ����͂Ȃ��B��w�E�Z��̕ʂł݂�ƁA��w�ւ̓��w�҂͑����X���ɂ��邪�A�Z��ւ̓��w�҂͋ߔN�����X���ɂ���B
�i�w���ł݂Ă݂�ƁA�����Q�N�ɂ͑�w�E�Z��ւ̐i�w����36.3���ł������̂��A���̌㑝���𑱂��A����17�N��51.5���ƂT�����A����19�N�ɂ�53.7���ƂȂ����B����ɁA����E���w�Z���������i�w���́A����19�N��76.3���ƂȂ��Ă���A���{�̍�������@�ււ̐i�w���̍���������������B
�܂��A�����Ȋw�ȁu����19�N�� �w�Z���瑍���v�ɂ��ƁA���a35�N�ɂ͒j�q14.9���A���q5.5���ƒj�����̑傫��������w�E�Z��ւ̐i�w�����A����18�N�ɂ͒j�q53.7���A���q51.0���ƂȂ�A�i�w���ɂ�����j�����͂Ȃ��Ȃ����Ƃ����������B
�y1-2�z��s�s�Œ��w�̊�]���}��
- �o�T
- �u��S��w�K��{�����E���������i���w���Łj�v�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[�i2006�j
- �����Ώ�
- �S���R�n��m��s�s�i����23����j�A�n���s�s�i�l���̌������ݒn�j�A�S���i���k�n���j�n �̏��w�T�N�� 2,726��
���w�T�N����Ώۂɒ��w�̊�]�������˂��������ʂ��݂�ƁA���w����]���鏬�w���̔䗦�͏��X�ɑ��������A1990�N��15.7������2006�N�ɂ�23.5����7.8�|�C���g���������B
�n��ʂɂ݂�ƁA������̒n��ɂ����Ă������X���ɂ��邪�A�Ƃ��ɑ�s�s�ł̐L�т��������A2006�N�ɂ�37.7���ƁA�S����̏��w�������w����]���Ă��邱�Ƃ��킩��B
2001�N����2006�N�ɂ����đ啝���ɂȂ����̂́A�w�K�w���v�̂̉����ɂ��2002�N�x����u�w�K���e�A���Ǝ����̍팸�v�u���S�w�Z�T�T�����v�����{����A�w�͒ቺ�����ƂȂ�ȂǁA�����w�Z�ւ̕s���f�������̂Ǝv����B
�y1-3�z���E���w���̒i�K�Ŕ��������n�E���n���ӎ�
- �o�T
- �u����17�N�x�o�ώY�ƏȈϑ����� �i�H�I���Ɋւ���U�Ԃ蒲��-��w����ΏۂƂ���-�v�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[�i2005�j
- �����Ώ�
- �S���̂S�N����w�ɒʂ���w�P�N���`�S�N����6,500��
��w����Ώۂɍs�����i�H�I���Ɋւ���U�Ԃ蒲�����݂�ƁA�u���n�E���n���ӎ����������v�̃s�[�N�́u���w���̂���v��40.0���A�����Łu���Z�P�N���v��30.2���ƂȂ��Ă���B���E���w���܂ł̒i�K�ł��łɔ��������n�E���n���ӎ����Ă��邱�Ƃ��킩��B
�@���ɁA�u��w�ł̐�U������ӎ����������v���݂Ă݂�ƁA�u���Z�R�N���v��29.6���A�u���Z�Q�N���v��29.4���ƁA���Z�Q�N���E�R�N�����قړ��������ƂȂ��Ă���B����Ɂu���Z�P�N���v�i17.3���j��������Ɩ�S���̂R�����Z����ɐ�U������ӎ����Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@�܂��A�u�i�w�����w���ӎ����������v�́A�u���Z�R�N���v��57.7�����s�[�N�ɁA�����Łu���Z�Q�N���v��24.0���ƂȂ��Ă���A��W�������Z�Q�N���ȍ~�ɐi�w�����w����̓I�ɍl���Ă��邱�Ƃ��킩��B
����ɑ��āu�E�Ƃ��ӎ����������v�́A���E���w�Z����i�u���w���̂���v�u���w���̂���v�̍��v�j��24.8���A���Z����i�u���Z�P�N���v�u���Z�Q�N���v�u���Z�R�N���v�̍��v�j��29.9���A��w�P�`�S�N���̍��v��25.0���A�u�܂��l���Ă��Ȃ��v��19.1���ƁA���قڎl������錋�ʂƂȂ��Ă���B
�y1-4�z�ی�҂̂W���A��w���ɉ��炩�̃����b�g����
- �o�T
- �u���Z���̐i�H�ɂ��Ă̒����v������w��w�o�c�E�����Z���^�[�i2006�j
- �����Ώ�
- �S��4,000�l�̍��Z�R�N���Ƃ��̕ی��
���Z���ƌ�̐i�H�Ɋւ��č��Z�R�N���̕ی�҂ɂ����˂����ʂ��݂�ƁA�u�N�ł���w�ɓ���鎞�ゾ�����w���o�Ă��債�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������ڂɑ��āA�u�S�������͎v��Ȃ��v�Ɓu�����͎v��Ȃ��v�����킹��ƁA��W���̕ی�҂���w���o�邱�Ƃɉ��炩�̃����b�g������ƍl���Ă��邱�Ƃ��킩��B
�@�u���i��Ƌ��̂Ƃ��w�Z�ɂ����Ăق����v�ɂ��ẮA20.8���̕ی�҂��u���������v���v�A54.3���̕ی�҂��u�����v���v�Ɠ����Ă���A���Z���ƌ�̐i�H�Ƃ��āA��w���C�w�Z�Ȃǂ̍�������@�ւɎ��i��Ƌ��̎擾�����҂��Ă���l�q������������B
�u���Z�𑲋Ƃ�����o�ϓI�Ɏ������Ăق����v�Ƃ������ڂɑ��ẮA�u�S�������͎v��Ȃ��v�Ɓu�����͎v��Ȃ��v�����킹��ƁA��R���̂Q�̕ی�҂��ے�I�ȉ����Ă���B����́A�q�ǂ����u�w���̊ԁv�܂��́u��E�ɏA���܂Łv�͌o�ϓI�ɖʓ|���݂Ă��悢�ƍl����e���U������Ƃ������������i�w�����x��Q��y2-2�z�Q�Ɓj�Ƃ���v����B
���̈���ŁA�u�����ʋA�ʊw���Ăق����v�u�ƒ�̌o�ϗ͂Ɍ��������i�H��I��łق����v�ɂ́A���ꂼ��66.3���A76.9���̕ی�҂��u���������v���v�܂��́u�����v���v�Ɠ����Ă���B
- �Q�l����
- �u����18�N�x�� �����Ȋw�����v�����Ȋw��
- �u����19�N�x�w�Z��{��������ɂ��āv�����Ȋw��
- �u��S��w�K��{�����E���������i���w���Łj�v�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[
- �u����17�N�x�o�ώY�ƏȈϑ����� �i�H�I���Ɋւ���U�Ԃ蒲��-��w����ΏۂƂ���-�v�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[
- �u���Z���̐i�H�ɂ��Ă̒����v������w��w�o�c�E�����Z���^�[

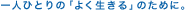
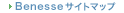

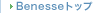
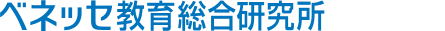



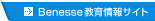
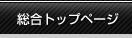
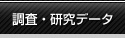
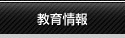

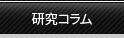

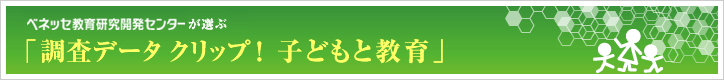
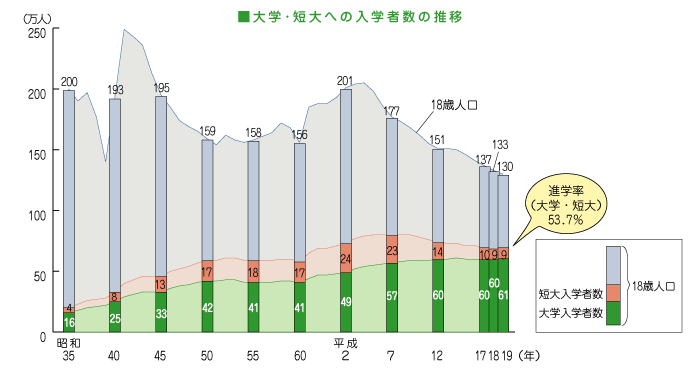
![���w�̊�]�i���w���A�n��ʁj](img/graph1_2.gif)