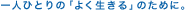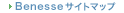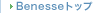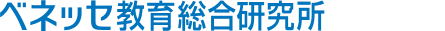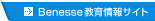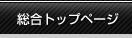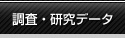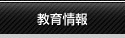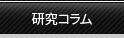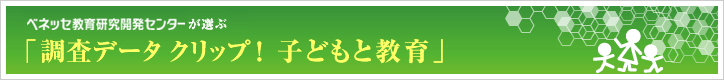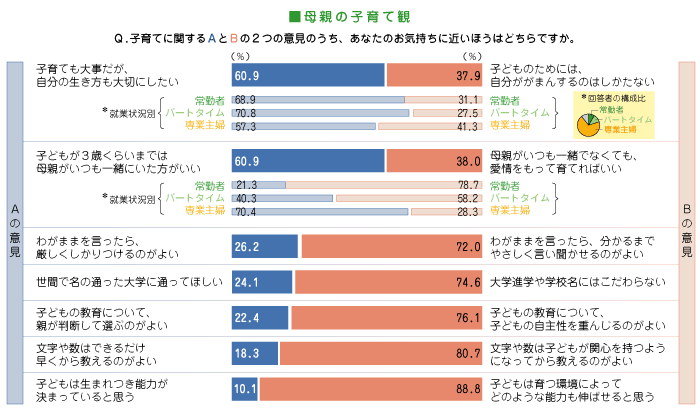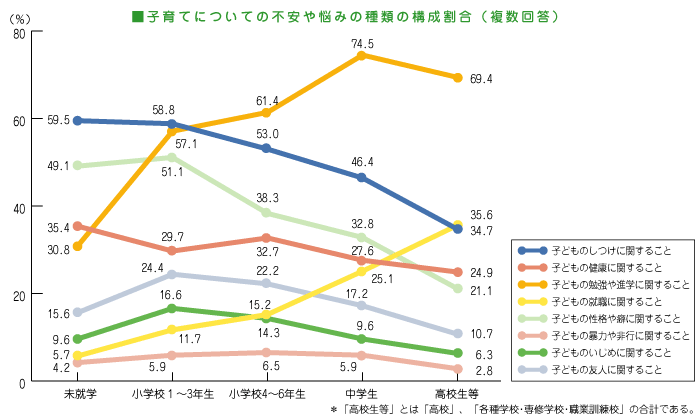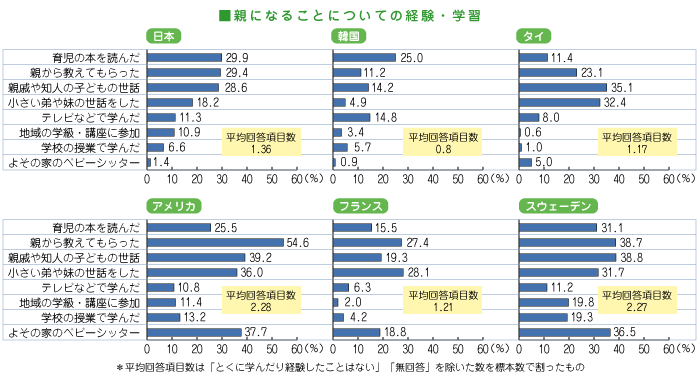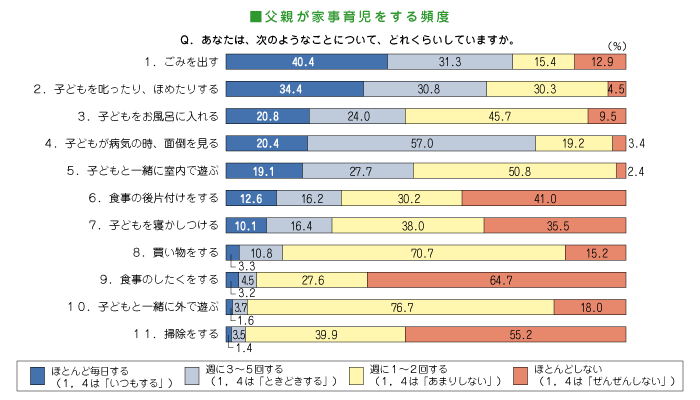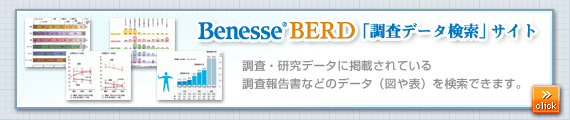�q��� �`��Q��`
|
�y2-1�z�U���̕�e���A�q��Ă������̐���������ɂ�����
- �o�T
- �u��R��c���̐����A���P�[�g���E���������v�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[�i2006�j
- �����Ώ�
- ��s���̂O�U�����`�U�ΏA�w�O�̓��c�������ی�ҁi��ɂ͕�e�j2,980��
��e�̎q��Ċςɂ��Ă����˂��������ʂ��݂�ƁA�U���̕�e���u�q��Ă��厖�����A�����̐���������ɂ������v�ƍl���Ă���B���̈���Łu�q�ǂ����R���炢�܂ł͕�e�������ꏏ�ɂ������������v�ƍl�����e���U���ɂ̂ڂ�B�����̐��������q�ǂ��̂��Ƃ������Ƃ���ɂ������ƍl���Ă����e�̎p������������B
�@��e�̏A�Əʂɂ݂�ƁA��Ύ҂ƃp�[�g�^�C���́u�q��Ă��厖�����A�����̐���������ɂ������v���x������䗦�������B����A�u�q�ǂ����R���炢�܂ł͕�e�������ꏏ�ɂ������������v�ɑ��ẮA��Ǝ�w�̎x�������|�I�ɍ����i70.4���j�A��Ύҁi21.3���j�A�p�[�g�^�C���i40.3���j�ƌ����ȍ����݂�ꂽ�B
�q�ǂ��̋���ɂ��ẮA�u�����␔�͎q�ǂ����S�����悤�ɂȂ��Ă��狳����̂��悢�v�i80.7���j�A�u�q�ǂ��̋���ɂ��āA�q�ǂ��̎��含���d��̂��悢�v�i76.1���j���Ƃ��ɂW���O��ƁA�q�ǂ��̎��含�ɔC���A�q�ǂ��̉\����M���Č�����e�������l�q������������B
�y2-2�z�q�ǂ��̐����ƂƂ��ɕω�����q��Ă̔Y��
- �o�T
- �u����16�N�x�S���ƒ뎙���������ʁv�����J���ȁi2006�j
- �����Ώ�
- �S����18�Ζ����̎����i����16�N12��1�����݁j�̂��鐢��1,608���сi�W�v�q�̐�1,376���сj
�q��Ăɂ��Ă̕s����Y�݂ɂ��Ă����˂��������ʂ��݂�ƁA�S�̂Ƃ��Ắu�q�ǂ��̕���i�w�Ɋւ��邱�Ɓv��54.8���Ƃ����Ƃ������A�����Łu�q�ǂ��̂����Ɋւ��邱�Ɓv�i52.3���j�A�u�q�ǂ��̐��i��ȂɊւ��邱�Ɓv�i40.5���j�ƂȂ��Ă���B
�q�ǂ��̊w�N�ʂł݂�ƁA�u�q�ǂ��̕���i�w�Ɋւ��邱�Ɓv�u�q�ǂ��̏A�E�Ɋւ��邱�Ɓv�ɂ��ẮA�w�N���オ��ɂ�Ċ����������Ȃ��Ă���A�Ƃ��Ɂu�q�ǂ��̕���i�w�Ɋւ��邱�Ɓv�́A�q�ǂ��̊w�N�����w����74.5���A���Z������69.4���ƂV���O��̐e���s����Y�݂�����Ă��邱�Ƃ��킩��B
�@����A���̑��̕s����Y�݂ɂ��ẮA���A�w���珬�w�Z�P�`�R�N���ɂ����āA�S�̓I�ɍ��������ƂȂ��Ă��āA�w�N���オ��ɂ�Č�������X���ɂ���B
�@�q�ǂ��̐����ƂƂ��Ɏq��Ă̕s����Y�݂��ω����Ă����l�q������������B
�y2-3�z���{�̎q��ā@�o�����玙��
- �o�T
- �u����16�N�x�E17�N�x�ƒ닳��Ɋւ��鍑�۔�r�����v�Ɨ��s���@�l �������������فi2006�j
- �����Ώ�
- ���{�A�؍��A�^�C�A�A�����J�A�t�����X�A�X�E�F�[�f����12�Έȉ��̎q�ǂ��Ɠ������Ă���e�A���邢�͂���ɑ�������l�i�e����1000�T���v���j
���{�A�؍��A�^�C�A�A�����J�A�t�����X�A�X�E�F�[�f���̂U�����̐e��ΏۂɁA�e�ɂȂ邱�Ƃɂ��Ă̌o����w�K�ɂ��Ă����˂��������ʂ��݂�ƁA���{�ł́u�玙�̖{��ǂv��29.9���Ƃ����Ƃ������A�����Łu�e���狳���Ă�������v�i29.4���j�A�u�e�ʂ�m�l�̎q�ǂ��̐��b�v�i28.6���j�̏��ɂȂ��Ă���B
�@���ۂ̌o�����Ƃ��Ȃ����ڂ��݂�ƁA�u�e�ʂ�m�l�̎q�ǂ��̐��b�v��28.6���A�u��������▅�̐��b�������v��18.2���A�u�悻�̉Ƃ̃x�r�[�V�b�^�[�v�͂킸��1.4���ŁA���̍��Ɣ�ׁA�o�����玙�̖{����w�Ԋ����������̂������I���B�؍������l�̌X�����݂���B
������̂S�����ł́A�u�e���狳���Ă�������v�������ƁA�u�e�ʂ�m�l�̎q�ǂ��̐��b�v�u��������▅�̐��b�������v�u�悻�̉Ƃ̃x�r�[�V�b�^�[�v�ȂǁA���ۂɎq�ǂ��̐��b�������o������ʂ��߂Ă���A�Ƃ��ɉ��ĂR�����ł́A�u�悻�̉Ƃ̃x�r�[�V�b�^�[�v�i�A�����J37.7���A�t�����X18.8���A�X�E�F�[�f��36.5���j�𑽂��̐e���o�����Ă��邱�Ƃ������I�ł���B
�y2-4�z���e�̎Q���A�Ǝ����玙
- �o�T
- �u��P����c���̕��e�ɂ��Ă̒������v�x�l�b�Z������琬�������i2006�j
- �����Ώ�
- ��s���i�����s�A�_�ސ쌧�A��t���A��ʌ��j�̂O�`�U�S�����i�A�w�O�j�̎q�ǂ��������e2,958��
���e�̉Ǝ��E�玙�ւ̎Q���̒��x�����������ʂ���A�u�قƂ�ǖ�������i��������j�v�̐��l���������ڂ����ɂ݂Ă����ƁA�u���݂��o���v�i40.4���j�A�u�q�ǂ�����������A�ق߂��肷��v�i34.4���j�A�u�q�ǂ��������C�ɓ����v�i20.8���j�A�u�q�ǂ����a�C�̎��A�ʓ|������v�i20.4���j�ƂȂ��Ă���B����A���ʂ́u�|��������v�i1.4���j�A�u�q�ǂ��ƈꏏ�ɊO�ŗV�ԁv�i1.6���j�A�u�H���̂�����������v�i3.2���j�A�u������������v�i3.3���j�ł������B���e�̉Ǝ��E�玙�ւ̎Q���́A�u���݂��o���v��ʂɂ���A�S�̓I�ɉƎ������玙�̂ق��ɐϋɓI�ł���Ƃ����悤�B
�܂��A�������ɂ��Ɓu�Ǝ���玙�ɍ��ȏ�ɂ�����肽���Ǝv���܂����v�Ƃ̎���ɁA�u�͂��v�Ɠ��������e�����i47.9���j����B������肽���Ǝv���Ă���Ǝ��E�玙�́A�u�q�ǂ��ƈꏏ�ɊO�ŗV�ԁv�i78.8���j�A�u�q�ǂ��ƈꏏ�Ɏ����ŗV�ԁv�i44.9���j�A�u�q�ǂ�����������A�ق߂��肷��v�i36.5���j�Ƃ������玙�Ɋւ��鍀�ڂ���ʂ��߂��B����������A�Ǝ��͂܂����Ĉ玙�ɂ�����肽�����e�����݂��Ă���B
- �Q�l����
- �u��R��c���̐����A���P�[�g���E���������v�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[
- �u����16�N�x�S���ƒ뎙���������ʁv�����J����
- �u����16�N�x�E17�N�x�ƒ닳��Ɋւ��鍑�۔�r�����v�Ɨ��s���@�l�@��������������
- �u��P����c���̕��e�ɂ��Ă̒������v�x�l�b�Z������琬������