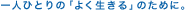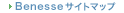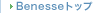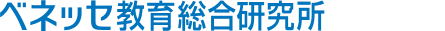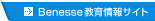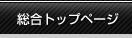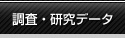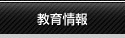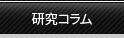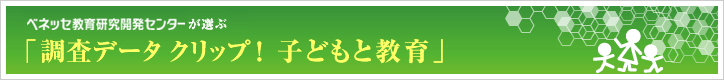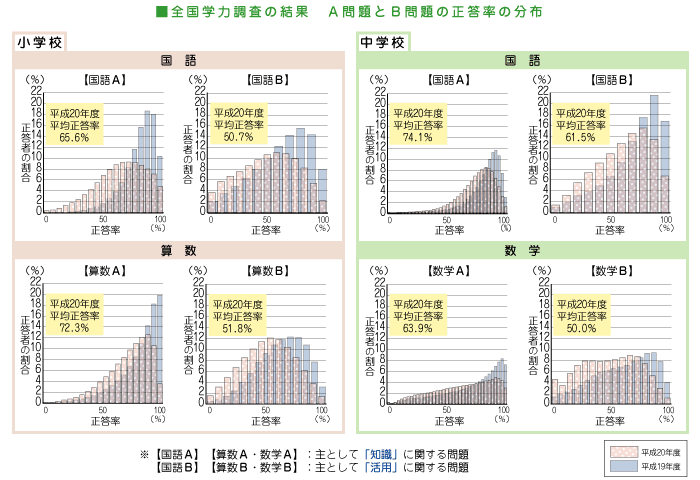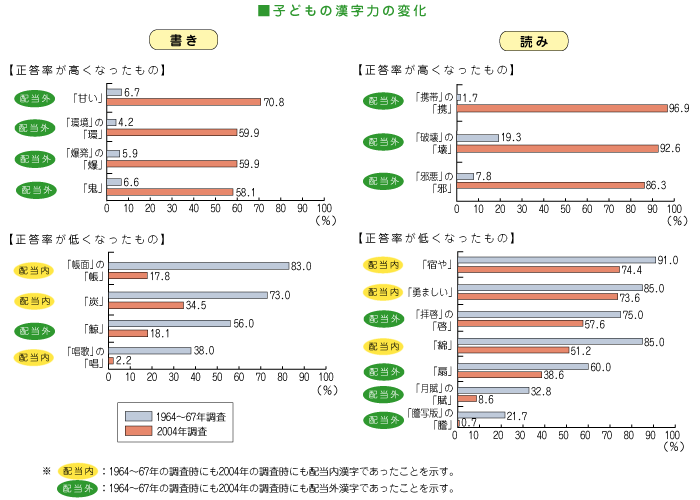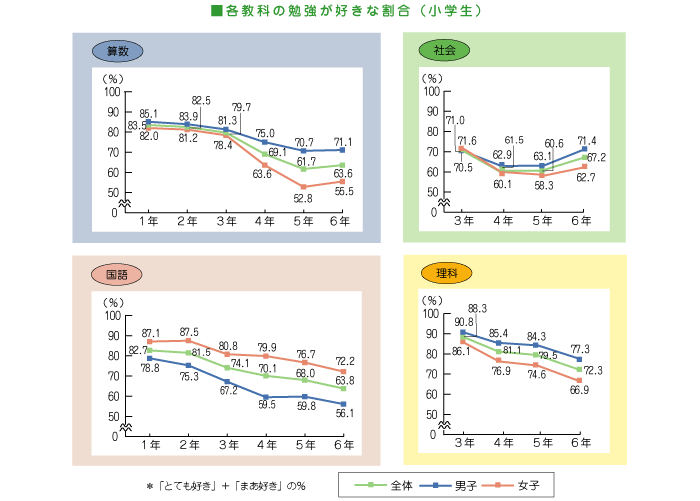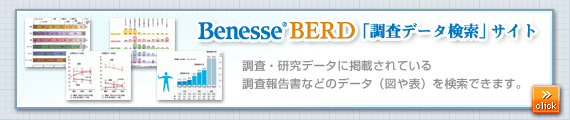�w�͂Ɗw�K �`��R��`
|
�y3-1�z�������̕��z�A���K���z�ɋ߂Â�
- �o�T
- �u����20�N�x �S���w�́E�w�K���� �������ʂ̃|�C���g�v�����Ȋw�ȁi2008�j
- �����Ώ�
- �S���y���w�Z�����z���w�Z��U�w�N�A���ʎx���w�Z���w����U�w�N�i��116���l�j�^
- �y���w�Z�����z���w�Z��R�w�N�A��������w�Z��R�w�N�A���ʎx���w�Z���w����R�w�N�i��108���l�j
����20�N�S���ɑS���̏����w�Z�Ŏ��{���ꂽ�u�S���w�́E�w�K�����v�̌��ʂ��݂�ƁA�S�̓I�ȌX���Ƃ��ẮA19�N�x�i�w�w�͂Ɗw�K�x��P��y1-1�z�Q�Ɓj���l�A��b�I�ȁu�m���v��₤�`���ɑ��āA�u���p�v����͂�₤�a���̕��ϐ��������Ⴂ���ʂƂȂ����B
����ł́A���w�Z�̂`���̕��ϐ�������65.6���Ȃ̂ɑ��āA�a��肪50.7����14.9�|�C���g�Ⴍ�A���w�Z�ł́A�`����74.1���ɑ��āA�a��肪61.5����12.6�|�C���g�Ⴍ�Ȃ��Ă���B�Z���E���w�ł́A���w�Z�̂`���̕��ϐ�������72.3���Ȃ̂ɑ��āA�a��肪51.8����20.5�|�C���g�Ⴍ�A���w�Z�ł́A�`����63.9���ɑ��āA�a��肪50.0����13.9�|�C���g�Ⴍ�Ȃ��Ă���B
�`���Ƃa���̐������̕��z��19�N�x�̒������ʂƔ�r���Ă݂�ƁA20�N�x�̐������̕��z�͐��K���z�ɋ߂Â��Ă���A19�N�x�Ɣ�ז�肪��������e�ł��������Ƃ�����������B���ϐ������ɂ��P���Ȕ�r�͂ł��Ȃ����A20�N�x�̕��ϐ�������19�N�x�Ɣ�ׂđS�ȖڂłW�`16�|�C���g�Ⴍ�Ȃ��Ă���B
�y3-2�z�����̓ǂݏ����̐������A����f
- �o�T
- �u�������k�̊w�K�����ƌ�b�̏K���Ɋւ����b�I���������v�������琭�����i2006�j
- �����Ώ�
- �S���̒��w�Z�P�N�� 3,018�l�i29�s���{�����琄�E�������w�Z29�Z�j
40�N�O�ɕ��������s�������������i1964�N�`67�N���{�j�Ɣ�r���āA�q�ǂ��̊����w�͂�����40�N�Ԃłǂ̂悤�ɕω��������ׂ��������ʁi2004�N���{�j���݂�ƁA�u�ǂ݁v�u�����v�Ƃ��ɐ��������傫���ω����Ă��邱�Ƃ��킩��B
40�N�O�Ɣ�א��������啝�ɏ㏸�����w�K�������݂�ƁA�u�����v�ł́u�Â��v��64�|�C���g�i6.7����70.8���j�A�u���v�́u�v��56�|�C���g�i4.2����59.9���j�A�u�����v�́u���v��54�|�C���g�i5.9����59.9���j�A�u�S�v��52�|�C���g�i6.6����58.1���j�㏸���Ă���B�܂��A�u�ǂ݁v�ł́u�g�сv�́u�g�v��95�|�C���g�i1.7����96.9���j�A�u���v�́u�ׁv��79�|�C���g�i7.8����86.3���j�A�u�j��v�́u��v��73�|�C���g�i19.3����92.6���j�㏸�����B
�@�}���K��Q�[���\�t�g�A�e���r�ȂǁA�q�ǂ�����������I�ɐe����ł��郁�f�B�A�ɓo�ꂷ��z���O�����̐������������Ȃ����Ƃ����悤�B
�t�ɁA���������啝�ɒቺ�����w�K�����́A�u�����v�ł́u���ʁv�́u���v�i65�|�C���g�j�A�u�Y�v�i39�|�C���g�j�A�u�~�v�i38�|�C���g�j�A�u���́v�́u���v�i36�|�C���g�j�A�u�ǂ݁v�ł́u�ȁv�i34�|�C���g�j�A�u�����v�́u���v�i24�|�C���g�j�A�u��v�i21�|�C���g�j�A�u���ʔŁv�́u���v�i21�|�C���g�j�u�q�[�v�́u�[�v�i17�|�C���g�j�Ȃǂł���A�������40�N�O�Ɣ�q�ǂ��������ڂ���@��̏��Ȃ��Ȃ��������̐��������ቺ���Ă���B
�������ɂ��ƁA�������o���邫�������́A�u�{�v62���A�u�}���K�v51���A�u�e���r�v44���A�u�e���r�Q�[���v24���ƂȂ��Ă���A�q�ǂ��̊����K���ɂ����̃��f�B�A���傫���e�����Ă��邱�Ƃ����������B
�y3-3�z�S�N���ȍ~�ɍ��܂�Z���̋��ӎ�
- �o�T
- �u���w���̌v�Z�͂Ɋւ�����Ԓ����v�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[�i2007�j
- �����Ώ�
- �S���̌������w�Z31�Z�̂P�N���`�U�N�� 8,897��
�Z���̕����ǂ̂��炢�D�����������˂��������ʂ��݂�ƁA�Z�����u�D���v�i�ƂĂ��D���{�܂��D���j�Ɠ����������́A�w�N���オ��ɂ�Č������A�P�N����83.5������A�U�N���ł�63.6���ƁA20�|�C���g�������Ă��邱�Ƃ��킩��B�Ƃ��ɁA�R�N������S�N���ɂ����Ă̌������傫���A���w�N�ł܂���������������l�q������������B
�@�j���ʂɂ݂�ƁA�P�N������R�N���܂ł͂��܂荷���Ȃ��̂ɑ��āA�S�N���ȍ~�͏��q�́u�D���v�̊������傫���������A���ӎ������܂邱�Ƃ��킩��B
����A�Z���Ƃ��킹�č���A�Љ�A���Ȃ̕����ǂ̂��炢�D�����������˂����ʂ��݂�ƁA����Ɨ��Ȃ͎Z���Ɠ��l�Ɋw�N���オ��ɂ�āu�D���v�̊������������A�j���ʂł́A����͏��q�A���Ȃ͒j�q�̂ق����u�D���v�̊����������Ȃ��Ă���B�Љ�́A���ΓI�ɂ݂Ēj�����͏������A�w�N�ɂ��Ⴂ�����܂�傫���Ȃ��X�����݂���B
- �Q�l����
- �u����20�N�x �S���w�́E�w�K���� �������ʂ̃|�C���g�v�����Ȋw��
- �u�������k�̊w�K�����ƌ�b�̏K���Ɋւ����b�I���������v�������琭����
- �u���w���̌v�Z�͂Ɋւ�����Ԓ����v�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[