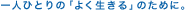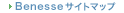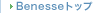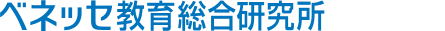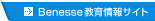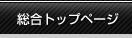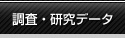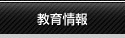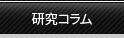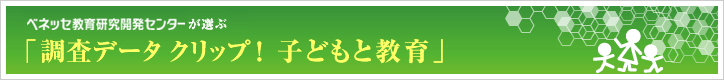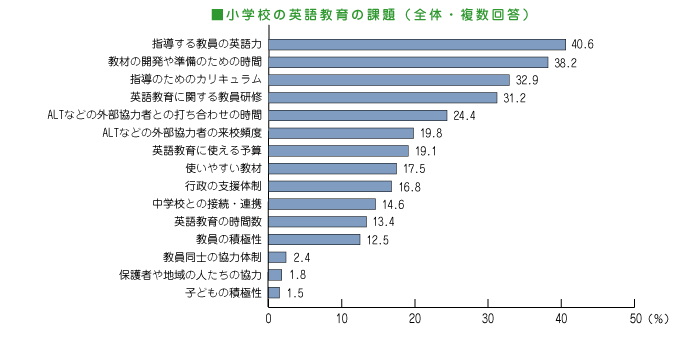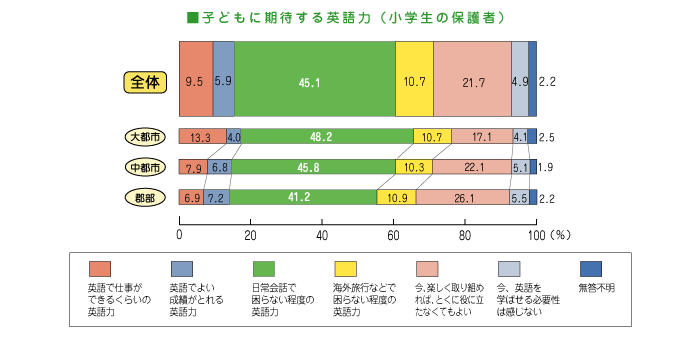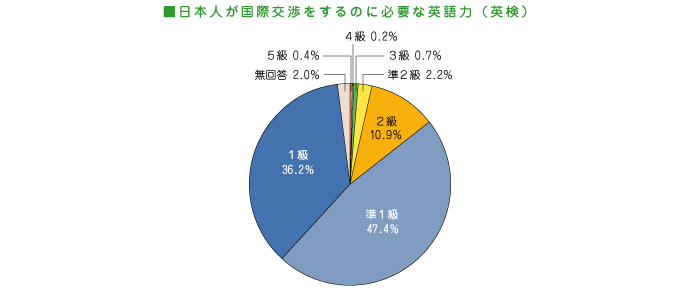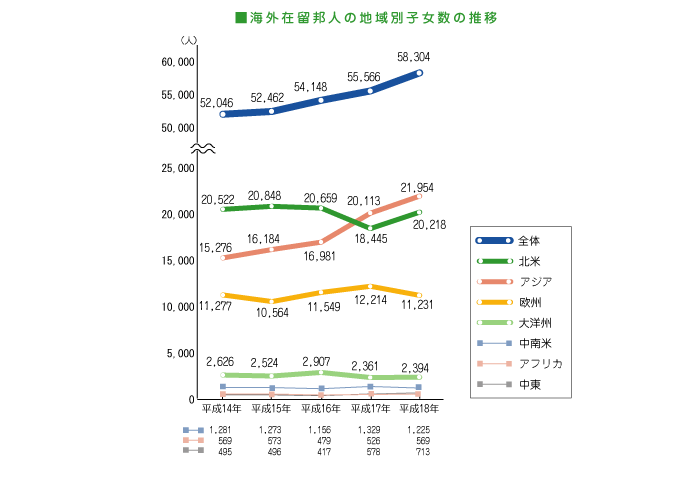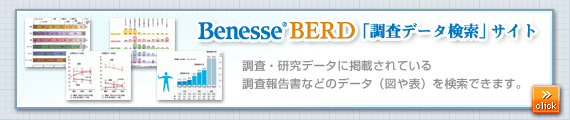�p�ꋳ�� �`��Q��`
|
�y2-1�z���w�Z�p��A�����̉p��͂⋳�ޏ����̂��߂̎��Ԃɉۑ�
- �o�T
- �u��P�w�Z�p��Ɋւ����{�����i���������j�v�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[�i2007�j
- �����Ώ�
- �S���̌������w�Z�̋����i������C�j3,503��
�S���̌������w�Z�̋�����ΏۂɁA�p�ꋳ����s����ł̉ۑ�ɂ��Ă����˂��������ʂ��݂�ƁA�S�̂ł͖�S���̐搶���u�w�����鋳���̉p��́v�i40.6���j�A�u���ނ̊J���⏀���̂��߂̎��ԁv�i38.2���j�������Ă���A�����ŁA��R���̐搶���u�w���̂��߂̃J���L�������v�i32.9���j�A�u�p�ꋳ��Ɋւ��鋳�����C�v�i31.2���j�������Ă��邱�Ƃ��킩�����B
������A�p�ꋳ��̔N�Ԏ����ʂɂ݂�ƁA�N�Ԏ����������ꍇ�ɂ́A�u���ނ̊J���⏀���̂��߂̎��ԁv�i49.1%�j�A�uALT�Ȃǂ̊O�����͎҂Ƃ̑ō����̎��ԁv�i34.3���j�A�u���w�Z�Ƃ̐ڑ��E�A�g�v�i21.5���j�Ƃ������A�p�ꋳ��̎��{��̉ۑ肪�����F������A����A�N�Ԏ��������Ȃ��ꍇ�ɂ́A�u�w���̂��߂̃J���L�������v�i37.2���j�A�uALT�Ȃǂ̊O�����͎҂̗��Z�p�x�v�i24.3���j�A�u�p�ꋳ��̎��Ԑ��v�i19.4���j�ȂǁA�p�ꋳ����{�ȑO�̉ۑ肪�����F�������X���ɂ������B
�y2-2�z�s�s���̐e�قǁA�q�ǂ��ɍ����p��͂�����
- �o�T
- �u��P�w�Z�p��Ɋւ����{�����i�ی�Ғ����j�v�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[�i2007�j
- �����Ώ�
- ���P���`���U���̎q�ǂ������ی�� 4,718��
���w���̎q�ǂ������ی�҂�ΏۂɁA�q�ǂ��Ɋ��҂���p��͂ɂ��Ă����˂��������ʂ��݂�ƁA45.1%�̕ی�҂��A�q�ǂ��ɂ́u�����b�ō���Ȃ����x�̉p��́v��]��ł��邱�Ƃ��킩�����B���̈���ŁA21.7���̕ی�҂��u���A�y�������g�߂�A�Ƃ��ɖ��ɗ����Ȃ��Ă��悢�v�Ɠ����Ă���A�q�ǂ��Ɋ��҂���p��͕͂ی�҂̊Ԃł�������邱�Ƃ��킩�����B
�����n��ʂł݂�ƁA��s�s�ł́u�p��Ŏd�����ł��邭�炢�̉p��́v�i13.3���j�A�u�����b�ō���Ȃ����x�̉p��́v�i48.2���j�ȂǁA�����p��͂����҂��鍀�ڂŁA���s�s�E�S�����������������Ȃ��Ă���B����A���s�s�E�S���ł́u���A�y�������g�߂�A�Ƃ��ɖ��ɗ����Ȃ��Ă��悢�v�i���s�s22.1���A�S��26.1���j�Ƃ������ڂŁA��s�s���������������B
�@�n���ی�҂̎q�ǂ��ɑ���i�w���ҁA����ςȂǂ̈Ⴂ��A�p���K�v�Ƃ���d���̗L���Ȃǂ��A���Ȃ��炸�e�����Ă�����̂Ǝv����B
�y2-3�z�����p��͂����߂��鍑�ۃr�W�l�X�̐��E
- �o�T
- �u��Ƃ����߂�p��͒������v���c�@�l���ۃr�W�l�X�R�~���j�P�[�V��������i2007�j
- �����Ώ�
- ���ۃr�W�l�X�Ɍg���r�W�l�X�p�[�\���i�C�O�ՋƖ��o���҂Ȃǁj7,354���i�j��4,273���A����3,078���j
�����A���O�ŊO���ƐՂ���Ɩ��o���҂ȂǁA���ۃr�W�l�X�Ɍg���Љ�l��ΏۂɁA���g�̌o������u���{�l�����ی�������̂ɕK�v�ȉp��͂͂ǂ̂��炢���v�������˂��������ʂ��݂�ƁA���p�p��Z�\����i�p���j�ł́A�u���P���v��47.4���Ƃ����Ƃ������A�����Łu�P���v36.2���A�u�Q���v10.9���ƂȂ��Ă���B�u���P���v�Ɓu�P���v�����킹���83.6���ɂȂ�A�W���ȏ�̐l�����P���ȏ�̉p��͂��K�v�Ɗ����Ă��邱�Ƃ��킩��B
�܂��A�������TOEIC�̓_���ł����˂����ʂ��݂�ƁA�u900�_�ȏ�v�K�v���Ǝv���l�͑S�̂�25.7���ŁA����Ɂu800�_�ȏ�v�i24.0���j�A�u850�_�ȏ�v�i18.9���j�����킹��ƁA��V���̐l��800�_�ȏ�͕K�v���Ɗ����Ă��邱�Ƃ��킩��B
�p�����Q���i�������͑����j�ȏ�̉p��͂�L���鍂�Z���͑S�̂�27.8���i�w�p�ꋳ��x��P��y1-3�z�Q�Ɓj�Ƃ��������{�̍��Z���̉p��͂�A��w�܂Ŋ܂߂Ă�736.4�����i�w�p�ꋳ��x��P��y1-2�z�Q�Ɓj�Ƃ������O����̎��Ǝ�������l����ƁA���ۃr�W�l�X�ŋ��߂���p��͂Ƃ����ϓ_����́A�w�Z�ł̉p�ꋳ��ł͏\���ł͂Ȃ��ɂ���Ƃ�����B
�y2-4�z�C�O�ݗ��M�l�̏A�w�q�����A�A�W�A�ő���
- �o�T
- �u�C�O�ݗ��M�l���������v�v�O���ȁi2007�j
- �����Ώ�
- �C�O�ɍݗ�������{����
�O���Ȃ́u�C�O�ݗ��M�l���������v�v�������A�C�O�ݗ��M�l�̎q�����i�����w�Z�i�K�ɂ���q�ǂ��̐��j�̐��ڂ��݂Ă݂�ƁA����14�N�ȍ~�S�̂Ƃ��đ����������Ă��邱�Ƃ��킩��B�n��ʂɂ݂�ƁA�A�W�A��21,954�l�ł����Ƃ������A�����Ŗk�Ă�20,218�l�A���B��11,231�l�ƂȂ��Ă���B����17�N�ɃA�W�A������܂Ńg�b�v�������k�Ă��A��P�ʂƂȂ����̂������I���B
�@�k�Ă͕���17�N�ɂ��������������̂́A����18�N�ɂ͍Ăё����ɓ]�����B���B�A��m�B�A����āA�A�t���J�A�����͂��̂T�N�́A�قډ����ł���B
���������A�ݗ��M�l�������ʂɂ݂�ƁA�������ɃA�����J���O���i370,386�l�j�A����(125,417�l�j�A�u���W���i64,802�l�j�A�p���i60,751�l�j�ƂȂ��Ă���B�����́A����12�N�ɂ̓u���W���E�p���Ɏ����ő�S�ʂł������̂��A����13�N�ɂ͉p�����đ�R�ʁA����15�N�ɂ̓u���W�����đ�Q�ʂƂȂ����B���n��Ƃ̒����ւ̐i�o�ɂ��A�A�W�A�n��̍ݗ��M�l���N�X�������Ă���悤�����킩��B
- �Q�l����
- �u��P�w�Z�p��Ɋւ����{�����i���������j�v�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[
- �u��P�w�Z�p��Ɋւ����{�����i�ی�Ғ����j�v�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[
- �u��Ƃ����߂�p��͒������v���c�@�l ���ۃr�W�l�X�R�~���j�P�[�V��������
- �u�C�O�ݗ��M�l���������v�v�O����