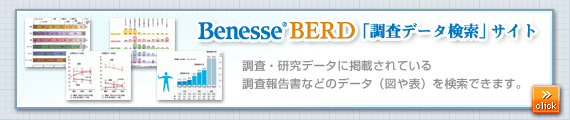�w�Z�E���� �`��R��`
|
�y3-1�z�����ӌ��́u�n�捷�Ȃ��v�u��b�I�ȓ��e���v�u���ׂĂ̎q�ǂ��Ɂv
- �o�T
- �u�w�Z����ɑ���ی�҂̈ӎ�����2008�@����Łv �x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[�E�����V���Ёi2008�j
- �����Ώ�
- �S���̏��Q���A���T���A���Q�������ی��5,399��
�S���̏����w���̕ی�҂�ΏۂɁA�w�Z����ɑ���ӎ��������˂��������ʂ��݂�ƁA(1)������e�̌���Ɋւ��Ắu�ǂ�Ȓn��ł��������������悤�A������e�͍�����߂��ق��������v��71.1���Ƒ����A�u�n��ɂ��Ⴂ�������Ă��A������e�͓s���{����s�撬�������߂��ق��������v��25.9����傫���������B�܂��A(6)�w�K���e�̑I���Ɋւ��Ắu�`������ł́A���ׂĂ̎q�ǂ��ɋ��ʂ�����e��������̂��悢�v���U�����Ă���A���ׂĂ̎q�ǂ��ɋ��ʂ̋�����e��]�ޕی�҂��������Ƃ��킩��B
(3)���ȏ��̃��x���ɂ��Ắu���ȏ��͊�b�I�ȓ��e�ɏd�_��u���č�����ق��������v���V�����A(4)���Ăق����w�͂ł́u���ȋ��Ȃ̊w�́v�i63.6���j�A(5)���₵�Ăق������Ƃł́u���ȏ��̊�b�I�Ȓm����g�ɂ�����Ɓv�i56.1���j�ƁA��b�I�Ȓm���E���e���d������ی�҂������B
(2)�w�Z�Ԃ̋����Ɋւ��ẮA�����ɂ��u���炪�����Ȃ�v�i65.4���j�Ƃ̈ӌ��������A(7)�w�Z����̕��S�Ɋւ��鎿��ł́A�ӌ��������ꂽ�B
�y3-2�z�q�ǂ��͗F�����W�E���Əd���A�ی�҂͐����w��������
- �o�T
- �u���w�Z�I���Ɋւ��钲���@����Łv�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[�i2008�j
- �����Ώ�
- �S���̌������w�Z�ɒʂ��U�N���Ƃ��̕ی�ҁi���w�U�N�� 1,501���A�ی�� 1,504���j
���w�U�N���̎����Ɂu�ʂ��������w�Z�v���A���̕ی�҂Ɂu�q�ǂ���ʂ킹�������w�Z�v�������˂����ʂ��݂�ƁA�u�ƂĂ������v���v�̔䗦�������̂́A�q�ǂ��ł́u���Ԃ͂���₢���߂��Ȃ��v�i78.3���j�A�u�킩��₷�����Ƃ����Ă����v�i76.3���j�A�u���w�Z�̗F��������������s���v�i61.2���j�ƂȂ��Ă���A�q�ǂ��́A�F�����W����Ƃ̂킩��₷�����d�����Ă��邱�Ƃ��킩��B
����A�ی�҂ł́A�u�킩��₷�����Ƃ����Ă����v�i80.9���j�A�u���Ԃ͂���₢���߂��Ȃ��v�i75.7���j�A�u�������Ƃ������猵�����������Ă����v�i60.6���j�̔䗦���U������W���ƍ����B��ʂQ���ڂ͎q�ǂ��Ɠ����ł��邪�A�ی�҂́A�F�����W����Ƃ̂킩��₷���ɉ����A�����ʂł̎w�������҂��Ă���l�q������������B
�y3-3�z�w���͕s�����������܂�闝�R�A���ς͊��̕ω��A�����͎��ԕs��
- �o�T
- �u����ψ���E�w�Z�@�l�A���P�[�g�A����ы����A���P�[�g�v���t�{�i2005�j
- �����Ώ�
- ����ψ���E�w�Z�@�l 1,084�A�]���拳�� 129�l�A�S���p�ꋳ�� 131�l
�����̗̍p���ԓ��Ɋւ���A���P�[�g��������A�u�w���͕s�����������܂�闝�R�v�������˂��������ʂ��݂�ƁA�u�ی�҂�k�̋���������ڂ��������Ȃ������߁v�Ƃ������A�s���{������ψ����61.7���A�s�拳��ψ����49.8���Ƃ������ʂɂȂ����B�����Łu��������e�����l�ɂȂ�A�]���̋���m�E�n�E�ł͒ʗp���Ȃ��Ȃ��Ă��邽�߁v�i�s���{������55.3���A�s�拳��51.9���j���|�C���g�������B
����A�����ł́u�����̋Ɩ�����E�����ԋΖ�����茤���⎩�Ȍ[���̎��Ԃ��Ƃ�Ȃ����߁v���A58.8���Ƃ����Ƃ��|�C���g�������B���̍��ڂɊւ��ẮA�s���{������17.0���A�s�拳��27.1���ƁA�����ɔ�ׂĂ��Ȃ�|�C���g���Ⴍ�A���ԕs����Ɋ����錻��̋����Ƌ���ψ���Ƃ̈ӎ�������������ɂȂ����B
�܂��A����ψ���A�����Ƃ��ɂS���O�オ�u�����Ƃ��Ă̓K�������������҂͏�Ɉ��䗦�̗p�҂̒��ɑ��݂��Ă��܂����߁v�i�s���{������38.3���A�s�拳��45.4���A����41.2���j�Ɖ��Ă���B
�y3-4�z���ȕ]���͂قڑS�Z�Ŏ��{�A�w�Z�W�ҕ]���͂܂�����
- �o�T
- �u�w�Z�]���y�я��̎��{�i����18�N�x�� �������ʁj�v�����Ȋw�ȁi2008�j
- �����Ώ�
- �S�Ă̓s���{���E�s�撬������ψ���y�ёS�Ă̍��������w�Z�i��w�A�������w�Z�������j
�w�Z�]���y�я��̎��{�ׂ����ʂ��݂�ƁA����18�N�x�́u�����w�Z�ɂ����鎩�ȕ]���v�̎��{����98.0���ƁA�قڂ��ׂĂ̌����w�Z�Ŏ��ȕ]�����s���Ă��邱�Ƃ��킩��B�w�Z��ʂɂ݂�ƁA�c�t���ł�85.7���A���w�Z�ł�99.7���A���w�Z�ł�99.6���A�����w�Z�ł�99.5���̊w�Z�Ŏ��ȕ]���Ɏ��g��ł���B
�@���ȕ]�������{�����w�Z�̂����A�]�����ʂ��u�ی�҂ɍL�����\���Ă���v�w�Z��45.2���i�����ΏۍZ�S�̂�44.3���j�ł������B���\���@�Ƃ��ẮA�u�w�Z�ւ�𗘗p�v��79.1���A�u�z�[���y�[�W�𗘗p�v��31.4���ƂȂ��Ă���B
����A����18�N�x�́u�����w�Z�ɂ�����w�Z�W�ҕ]���v�̎��{����49.1���ƑS�̂̔������x�ɂƂǂ܂��Ă���B���{�����w�Z��ʂɂ݂�ƁA�c�t���ł͖�Q���A���E���w�Z�ł͖�T���A���Z�ł͖�V���ƂȂ��Ă���B
�@���̂����A�]�����ʂ��u�ی�҂ɍL�����\���Ă���v�w�Z��38.7���ł���A����͒����ΏۍZ�S�̂�19.0���ł���B���\���@�Ƃ��ẮA�u�w�Z�ւ�𗘗p�v��76.7���A�u�z�[���y�[�W�𗘗p�v��34.4���ƂȂ��Ă���B
�@
- �Q�l����
- �u�w�Z����ɑ���ی�҂̈ӎ�����2008�@����Łv�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[�E�����V���� ��������
- �u���w�Z�I���Ɋւ��钲���@����Łv�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[
- �u����ψ���E�w�Z�@�l�A���P�[�g�A����ы����A���P�[�g�v���t�{
- �u�w�Z�]���y�я��̎��{�i����18�N�x�� �������ʁj�v�����Ȋw��

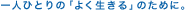
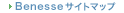

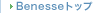
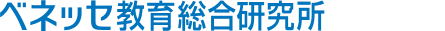



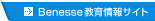
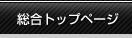
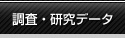
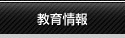

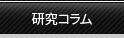

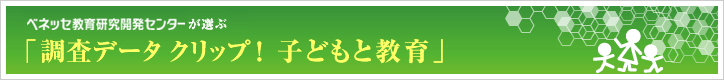
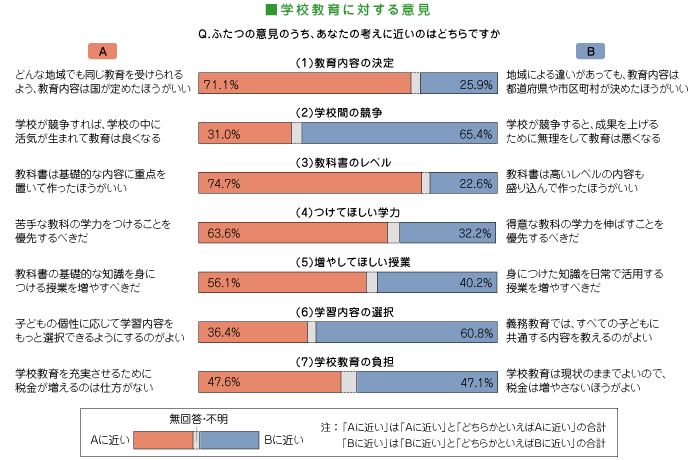
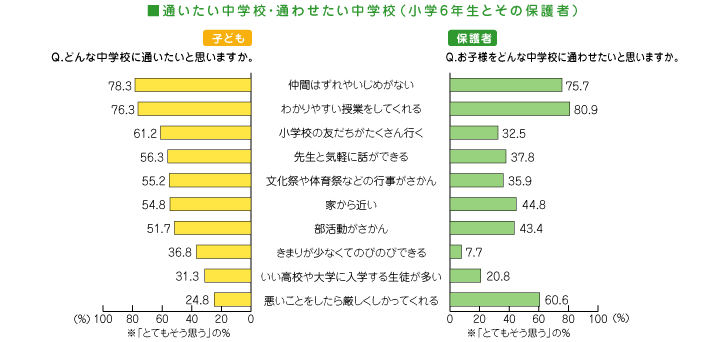
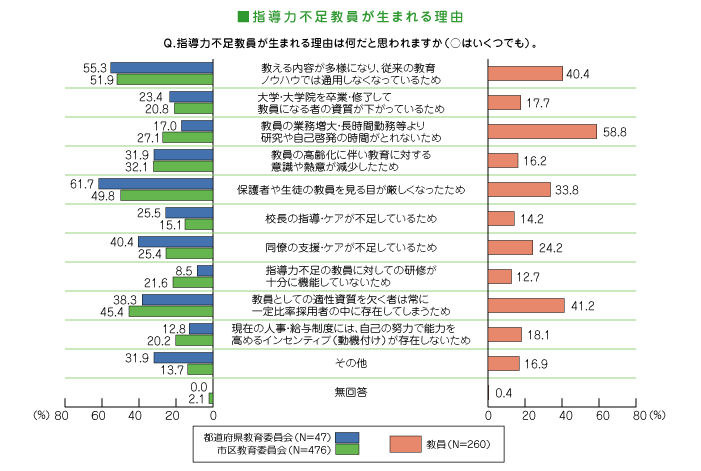
![�w�Z�]���̎��{�ƌ��\�̏�](img/graph3_4.gif)