様々な場所で色とりどりに活躍している20代、30代。彼らのインタビューを通して、これからの社会で活躍し、「Well-being」に生きるためのヒントを探っていきます。
今回は、株式会社STYZ、一般社団法人Earth Company、一般社団法人ELABと3つの組織で働く繋奏太郎さんにお話をうかがいました。
知らないことに出会う喜びを感じながら、
人と人とを繋いで社会課題の解決を促進したい

- 繋 奏太郎
株式会社STYZ ファンドレイザー
一般社団法人Earth Company ファンドレイザー
一般社団法人ELAB 理事
1997年生まれ。青森県出身。創価大学法学部在学中に株式会社STYZのインターンとして働き始める。2020年、同大学卒業後、同社の正社員となり、非営利団体を中心とした寄付金の調達・ブランディング・コンサルティングを行う。その傍ら、一般社団法人Earth Companyでは、寄付金調達の支援を、一般社団法人ELABでは、U25の社会人・学生を中心としたEGAKU®プログラム(アートワークショップ)の提供に携わっている。
3つの組織に所属し、社会課題の解決に挑む
私は、3つの組織に属し平行して仕事をする、いわゆるパラレルワーカーです。働く時間の7割を費やしているのは、株式会社STYZ(以下、STYZ)でのファンドレイジング業務です。
ファンドレイジングとは、NPO法人などの非営利団体の運営資金を、個人または法人から寄付という手段で調達すること。私はそのファンドレイジングを行うファンドレイザーとして、支援団体の資金調達の一環として、ブランディング・マーケティングも担当しています。これまで70団体の資金調達のため、約4000人の方から寄付金を集めました。
高校時代から社会課題に関心があり、大学在学中にSTYZにインターンとして働き始め、大学を卒業後、2020年からは正社員になりました。しばらく働いているうちにファンドレイジングは、新人アイドルを応援するファンに似ている!と思うようになりました。
私はアイドルオタクなのですが、グループの中でも特に自分の応援しているメンバーを「推し」と言い表します。なぜそのメンバーを「推し」たくなるのかといえば、ステージ上で頑張っている晴れの姿だけでなく、ブログ等を通じて日々の努力や葛藤も知り、その姿に自分自身が勇気づけられるから。それと同じように、社会課題に懸命に取り組む団体の思いや物語を伝える仕組みがファンドレイジングでも実現できれば、団体を支援してくれる方が増えるのではないかと考えました。そこで、「どのような思いで団体を立ち上げたのか、日々どのような活動をしているのか」等、団体の内側が見えるような情報発信を大切にしています。
そして、団体の代表の方から団体の設立経緯や活動への思いを詳しく聞き、それらをまとめた記事を発信しています。私の発信した記事をきっかけに、80人もの方々から寄付をいただいた団体もありました。
途上国での教育格差に取り組むも志半ばで帰国し、挫折を経験
非営利団体とその団体を支援する人を繋ぐ仕事は、自分に合っている仕事だと感じています。ただ、この仕事に巡り会うまでには、大きな挫折がありました。2018年、大学4年生の時、約半年間、ほとんど部屋から出ない時期がありました。
大学のプログラムでフィリピンでのフィールドワークに参加した私は、途上国のリアルを初めて目の当たりにし、途上国の教育に関心を持ちました。私自身、大学からの奨学金がなければ今の自分を切り開けなかったように、環境によって自身の可能性を狭めてしまう途上国の状況をなんとかしたいと思うようになりました。
フィリピンから帰国後、「トビタテ!留学JAPAN」に応募し、奨学金を得ながら、途上国の子どもの教育格差に取り組むe-Educationという団体の海外インターンとして働くことになりました。目的は、フィリピンのミンダナオ島で、映像教育の普及と現地の大学生が教育課題の解決に取り組むプロジェクトの立ち上げです。ただ、当時テロ組織の問題の影響で、ミンダナオ島でもテロ組織と政府軍の争いが起き、現地の治安が悪化。志半ばで活動の自粛をせざるを得ませんでした。
帰国後は、STYZでインターンとして働き、当時はジャーナリストの渡航費の調達をする業務に携わりました。その傍ら、途上国の教育格差の是正とは異なる分野で社会課題に取り組む組織を立ち上げたいと考え、NPO法人ETIC.という団体が運営する社会起業家を育成する「MAKERS UNIVERSITY」というプログラムに入りました。そこは、起業や社会問題解決などの目標を持つ若い世代が学び合うプログラムで、業界最前線の起業家であるメンターから、自分の起業プランにアドバイスをもらうことができました。
社会課題を解決する団体を立ち上げようとしたものの、自身で取り組む事業と向き合うことができていませんでした。そう思い悩んでいる間にも、仲間は次々と起業。事業が軌道に乗ってきたという様子も見聞きするようになり、焦りから、どんどん苦しくなっていきました。それに追い討ちをかけるように、メンターの方から、「あなたが考えている計画は、誰のための事業なのかわからない。ソーシャルビジネスに向いていないのでは?」と、自分でも課題だと感じていたことをズバリ指摘されてしまったのです。私に本気で考えてほしいからこそ、あえて厳しい言葉を口にしたと思うのですが、当時の自分には、自分の課題に向き合う余裕がありませんでした。ショックのあまり、STYZの仕事からも離れ、約半年間、何もできない状態になってしまいました。
絵を描くワークショップで自分が大切にしたいコトに気づく
そんな自分を救ってくれたのが、「EGAKU®」というアートワークショップでした。このワークショップは、自身で選んだ色の台紙に与えられたテーマに関する絵を自由に描き、他の参加者と描いた絵を鑑賞し合い、自分の生き方や働き方を見つめ直したり、感性や創造性を高めたりすることを目的にしています。お世話になっていた方に誘われ、興味半分で参加しました。
最初に参加した回のテーマは、「あなたを突き動かすもの」。私を突き動かすものは、「知らないことを知りたい」という思いです。それを宇宙や海のような青色で表現したいと思い、心の赴くままに筆をとりました。完成した絵を見ると、言葉では表現しづらい、自身の大切なことが表れていると感じました。自分が無知であることは幸せであり、いろいろな人と関わることで、社会課題の解決を促進していきたい。改めて、自分が大切にしたいことを、絵を描くことで認識できたのです。
ワークショップに参加して自分の関心が明確になっていく中、インターンとして働いていたSTYZの社長から「会社に戻ってこないか?」と声を掛けられました。目標としていた起業を果たせず、自分の都合で会社を離れてしまいましたが、ひきこもりになった期間も、社長は時々食事に誘ってくれていました。ずっと気にかけてくれていた社長から「ファンドレイジング」の業務内容を聞き、「知らないことを知りたい」「社会課題の解決に携わりたい」という自分自身の思いが通ずる仕事だと感じ、もう一度、ソーシャルビジネスの世界にチャレンジしようと思ったのです。
パラレルワークだからこそ感じられる
複数の仕事を相互に成長させられる強み
大学時代は、自分が起業したいと考えていましたが、今は、起業家や団体を支える右腕になりたいと思っています。また、私は、1つのことにすべての力を注ぐより、社会課題の解決を目指す多くの団体と関わりながら、次々と新しいことに出会い、多くの団体の社会的意義を世間に伝え、支援してくださる方を広げるという仕事を通して、様々な社会課題の解決を促進できることに幸せを感じています。新しいことを知りたいという好奇心を満たし、自分の強みを生かせる場所を選んだ結果、STYZの他にも2つの会社に籍を置いています。
2020年2月からは、一般社団法人Earth Company(以下、Earth Company)で、インドネシア・バリの社会起業家を支援するためのファンドレイジングにも関わっています。大学時代からの友人がこの団体で働いており、「うちのファンドレイジングを手伝ってくれないか」と誘われたのがきっかけで、現在は、継続寄付者獲得の手伝いをしています。
STYZとEarth Companyでは、どちらも資金調達が仕事ですが、組織が違うことによって、業務範囲が異なります。STYZでは、3〜4か月と短期間の資金調達支援が中心ですが、Earth Companyでは年単位での資金調達が中心となるため、LPの作成や全体スケジュールを見たリサーチ、実行支援などなど、STYZとは異なる観点での知見を得られます。また、STYZの仕事で様々な団体から学んだ事業の進め方などを、Earth Companyに還元しています。そうしたことができるのが、パラレルワークの魅力だと思います。
また、「EGAKU®」のワークショップを主宰する一般社団法人ELABにも所属し、中高生を中心とした25歳までの若い世代に向けて、アートによる学びを通じて、未来を創り出す力を育むアートワークショップを提供する仕事もしています。自分がこのワークショップで自分を取り戻せたように、若い年代から自分の感情や未来と向き合い、自分の選択を自身で正解にする「生きるチカラ」を養うことができる場をつくりたいと考えています。
様々な人たちを繋いで、 社会課題を解決できる基盤をつくりたい
振り返ると、幼い頃から私は両親から何かを強制されることなく、自分の選択を重ねてきました。また、兄弟がおらず両親が商売をしていたこともあり、一人で何かに取り組むことに早くから慣れ、自分の興味や関心に没頭できたのも、今の自分に影響していると思います。
今後は、行政、非営利団体、民間企業、研究所、アートなど、様々な人たちを繋いで、社会課題を解決できる基盤をつくりたいと考えています。2021年7月、世界を代表する政治家や実業家が一堂に会し、世界経済や環境問題など幅広いテーマで討議する世界経済フォーラム(ダボス会議)の下部組織に、ファンドレイザーとして参加する、名誉な機会を得ることができました。そうした場で、世界で活躍する人たちとつながりを築き、今後の自分の取り組みに生かしたいと考えています。
夢中になれるものができた今、誰かと自分を比べる必要がなくなり、とても楽になりました。若い世代の方には、自分とたくさん向き合ってほしいと思います。ぜひ、皆さんも自分の好きな部分も嫌いな部分も受け止めてみてください。好きな部分を突き詰めて考えることは、自分が幸せに生きる道を見つけることに繋がります。また、失敗は実験だったと捉え、ポジティブに考えてみましょう。失敗から生じる感情はいろいろありますが、感情的になりすぎず、自分の気持ちの一つひとつを冷静に受け止め咀嚼し、次への原動力に変えて、自分の幸せを見つけてほしいと思います。
これは皆さんへのメッセージでもあり、これからも自分が大事にしたい言葉です。
編集後記
名字の「繋」という字のごとく、人と人とを繋ぐお仕事をされている繋さん。今回のインタヴューでは、大学時代に経験した挫折も包み隠さずに話してくれました。しかし、その挫折経験があったからこそ、自分の本当の気持ちに向き合い、ファンドレイジングという「天職」に巡り会えたのだと思いました。また、ご自身も若いのに、25歳以下の若い世代を応援したいという気持ちに感銘を受けました。自分が先輩方から受けたように、人の成長を支えることが、自分の成長にも繋がる。そうした繋さんの思いは後輩にも伝わり、その輪はさらに広がっていくのではないかと感じました。
2021年6月29日取材
【新しい時代のWell-being】記事一覧
-
■
本当の自分の心を見つめ、誰もが幸せを感じられる社会に
ライフコーチ 佐伯 早織 -
■
社会への貢献は存在証明|見失ったアイデンティティを取り戻し生きる意味を見つけるまで
Plusbase inc. 創業者 / 看護師 ウィム・サクラ -
■
リサイクル率日本一の町で見つけた私の活躍場所|自ら見聞きした環境・地域の「リアル」がキャリアのヒントに
合作株式会社 地域連携事業部 ディレクター 藤田 香澄 -
■
ラップで心の病について発信し、社会の誤解をなくす
豊郷病院 精神科 作業療法士 佐々木 慎 -
■
中学校の地域学習から始まった。地元・伊豆での「幸せ」探し
伊豆市役所職員 飯塚 拓也 -
■
人と人をつなげていくことで、富田林市を笑顔が溢れる場所に
元富田林市職員 納 翔一郎 -
■
技能五輪全国大会・国際大会(世界大会)で活躍!周囲の協力を力に、自身の理想の姿へ向かっていく
日産自動車株式会社 事業投資部門 下原 侑也 -
■
エンジニアから新規事業開発へ 社内外との共創プロジェクトで価値を生み出す
日揮ホールディングス株式会社 サステナビリティ協創部 田中 悠太 -
■
理由なき大学進学に疑問を持ち、飛び出た日本 カナダで数学教師になり、生徒が主体となる授業を目指す
カナダの公立高校数学教員 梅木 卓也 -
■
「留職」で出会った私の使命 研究職から転向し、ビジネスで社会課題解決に挑む
日本電気株式会社(NEC) ビジネスデザイン職 松葉 明日華 -
■
「創薬」という大きな目標を追い求めながらも 日々の成長を大切に、一歩を積み重ねていく
大手製薬会社勤務 Bさん -
■
「誰かのために書く」を胸に単身パリへ ビジネスパーソンと書家であり続ける自分だけの道
アクセンチュア株式会社 書家 小杉 卓 -
■
誰も着手していない社会課題に信念を持って取り組んでいくことが自分の想いを世界にひろげる
株式会社manma 創業者 新居 日南恵 -
■
予測できない未来を選ぶ 釜石で課題に挑み続けた9年間
青森大学社会学部 准教授 石井 重成 -
■
周囲の人々を巻き込みながら多くの人に「楽しい」を届けたい
株式会社マンガボックス エンジニア こうたけ りな -
■
自分の選択に自信と責任を持ち、女性として着実に成長できる場所を選ぶ
大手金融会社 Aさん -
■
「自分の幸せは何か」に向き合い 自分が誰を笑顔にしたいかを考え抜く
一般社団法人 歓迎プロデュース 理事 根岸 えま -
■
自分の好奇心を大切にしながら社会貢献をしていきたい
外資系大手IT企業 エンジニア 河村 聡一郎 -
■
どんなに小さな一歩でも、動き出すことが自分の世界を広げ、ほんの少しでも世界に影響をあたえる
軽井沢風越学園 教員 根岸 加奈 -
■
「選んだ道を正解にする」自分を信じて進路を選択し、事業を生み出す
株式会社ABABA(アババ) 代表取締役 久保 駿貴


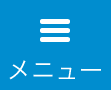
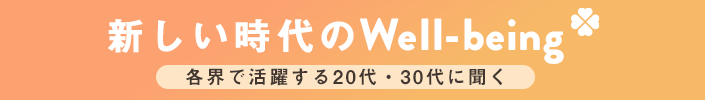

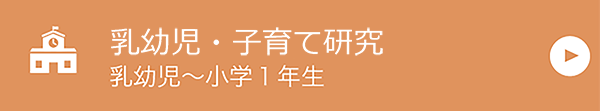
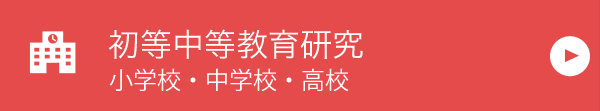

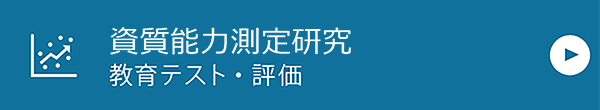
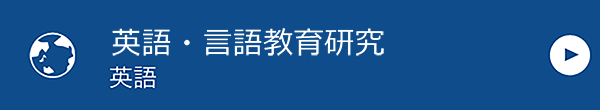
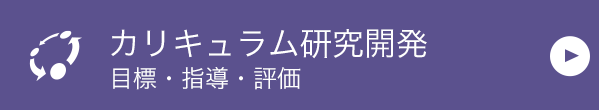
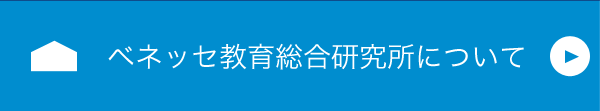
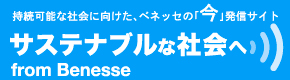
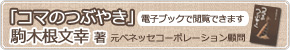
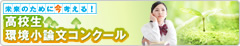
![ベネッセ教育総合研究所[公式ツイッター]](/images_sp/btn/btn_tw.png)