様々な場所で色とりどりに活躍している20代、30代。
ベネッセ教育総合研究所では、活躍する20代、30代のメディア発信に取り組んでいる、株式会社ドットライフおよび株式会社ユニークの協力のもと、より多様で幸せに活躍する方にインタビューを行いました。
彼らのインタビューを通して、これからの社会で活躍し、「Well-being」に生きるためのヒントを探っていきます。
今回は、富田林市の魅力発信に取り組む納翔一郎さんにお話をうかがいました。
人と人をつなげていくことで、富田林市を笑顔が溢れる場所に

- 納 翔一郎
1990年生まれ
元富田林市職員
20歳で富田林市役所に入庁。2017年、全国でも先駆け事例となる市民参加型インターネット生配信番組「富田林テレビ」を開設。個人活動として、実名SNSの運用などによる情報発信に取り組むかたわら、地域や公務員同士をつなげる様々なコミュニティ活動も多数行っている。2023年2月より民間企業へ転職し、カスタマーサクセスの担当へ。
富田林市の魅力をもっと伝えたいと公務員の道へ
大阪府富田林市で生まれ育ちました。地域の子ども会に入ったり盆踊りに参加したり、友達との遊び場として常に「地域」がありました。地域の大人たちとも、ごく普通に挨拶をして交流をする関係でした。
小中学校ではサッカーや野球に打ち込む一方、勉強には全く興味がありませんでした。早くボールを蹴りたいのに、なぜ机に向かっていなければいけないんだと感じていましたね。周りから叱られることも増え、徐々に勉強が嫌いになりました。
高校生になってファストフードチェーン店でアルバイトを始めました。仕事をする中で笑顔が溢れるお客様たちの姿を見て、ふと「自分が生まれ育った富田林市もずっとこうであってほしい」という思いが生まれたんです。
勉強は相変わらず嫌いで、このまま就職できないかと考えていました。しかし周囲はみんな進学するため、一番仲が良い友達が進学する大学の同じ学部に入りました。
大学に入ってから、一人旅を始めました。観光で他の地域を訪れる中で、いつの間にか、富田林市と比べている自分がいました。外の世界を知ることで、改めて富田林市の魅力に気づきました。たとえば、立地。大阪市内から30分圏内にあり、通勤にも便利です。観光地としても、ドラマのロケ地になるような古い町並みがあります。他にも主要産業が農業だとか面白い面がたくさんあるのです。でも外にその魅力が伝わっていないし、中にいる住民でさえちゃんと知りません。もっとこの魅力を内外に伝えていくためにはどうすればいいんだろうと考えました。
そして思いついた一つの道が、公務員でした。地域に関わる仕事はいろいろありますが、俯瞰して全体に携われる仕事が一番良いと考えたのです。思い立ったが吉日、当時は大学1年生でしたが、すぐに大学を辞める手続きをしました。大学で勉強を続けるよりも、働く方が生き生きと楽しい人生を送れると思ったからです。それから公務員試験の勉強をするための専門学校に入学し、20歳で富田林市役所の職員となりました。

人をつなげられる存在になりたい
初めて配属されたのは課税課の窓口業務でした。市民と関わる仕事がしたいと思っていたので、やりたい仕事ができて嬉しかったですね。上司からは「まずはいろんな人とつながってみるといいよ」とアドバイスを受けました。この言葉を聞いて「つながり」が私のキーワードとなりました。
その後、地域イベントに顔を出したりSNSで市民とつながったり、なるべくつながりを作るようにしました。市役所内でも自主研究グループを立ち上げました。しかし、公務員業界には縦割りの文化があり、部署を超えた交流に否定的な人もいます。ちょっぴり心の中で行き詰まりを感じていたとき、大阪府庁への出向が決まりました。
大阪府庁では、50代のある管理職職員が主催する、若手を数百名規模で集めた交流会がありました。その人との出会いが私の人生の一番の転機です。考え方がひっくり返されましたね。その人は各市町村からきた出向者や大阪府庁の若手職員からお偉いさんまで、幅広い年齢層の人たちを集めている場に自分も連れていってくれたんです。私たち世代では普段会えない人たちとつながる機会を数多く与えてくれました。他にも「納ちゃんはこの人とつながったらいいと思うよ」と個人的に紹介をしてくれました。普通ならば50代のベテランが交流会の幹事をすることなどありません。つながりを作るために走り回る姿勢に感銘を受けましたね。これまで漠然とつながりを意識していただけでしたが、自分もいつかこうやって人をつなげられる存在になりたいという新たな目標が生まれました。それからは、気になるコミュニティがあればとりあえず参加してみて、人の特性や強みを知りながら、どうつなげたら相乗効果が生まれるか、考えるようになりました。
2年出向した後、市役所に戻り都市魅力課に配属されました。府庁時代に、ほぼ全市町村に友達ができたことで、今まで各自治体の担当部署に問い合わせていたこともSNS一本で聞けるようになりました。人とのつながりがリアルな業務に活きることを実感しました。
業務内容も、地域のプロモーションや広報など、まさにやりたかったことでした。プロモーションに関しては、動画配信で人の魅力を発信することを官民連携事業として取り組もうと考えました。数々の市民と交流する中で富田林市は、ちょっぴりお節介で、人情味のある「人」が魅力だと気づいたからです。
はじめは今までにない挑戦に市役所内から批判の声もありました。でも、今までのやり方に縛られる必要はないなと思って。どうすればできるのか、今までつながってきた人のつてをたどり、できる方法を考えるようにしました。
そこで始めたのがインターネット配信の「富田林テレビ」です。富田林テレビは、あえて面識のない市民3組ほどをゲストに呼び情報発信をするという番組で、そのゲスト同士もその場でつながってもらうという裏テーマも私は持っていました。放送後には、毎回大きな反響がありました。情報発信をしたいけれどもその仕方が分からないという市民の方々の課題を解決することもできました。

仕事以外でのつながりも大事にし続けました。つながりを生み出す上で大事にしていたのは、相手の「強み」を見つけること。そして、自分視点だけでなく広い視点で考えること。自分と何かをするだけだと広がりませんし、自分にできることだけでは限りがあります。他者同士をつなげることでもっと面白くなる可能性があるかもしれないという考えのもとで、コネクトしていきました。
一方でプライベートでは、結婚という大きなライフイベントを迎えました。家庭を持ったことでワークライフバランスも大事にするようになりましたね。また、妻がWebマーケティングに携わっていたのもあり、ライティングを教えてもらい、地方公務員ブロガーとしての活動を始めました。もっと公務員のイメージを変えるような情報発信をしたいと考えたからです。その後も、様々なSNSでの発信に力を入れていきました。
富田林市を愛が溢れる場にするために
現在は、商工観光課で富田林市の観光資源の魅力の掘り起こしや情報発信をミッションとして働いています。具体的には観光ガイドを作成したり、企業と連携して人流データの分析の実証実験をしたりしています。この実証実験も、つながりの中の一つから生まれたものです。
相変わらず公務員コミュニティや地域活動も進めています。特に注力しているのが、自分が住んでいる金剛地区のコミュニティ「KONGO BASE」。高齢化が進んでいるエリアで、空き家も多くあります。この地域で若者と共に「金剛地区で遊ぶ」をコンセプトに活動をしています。

私が目指すのは、富田林市を愛が溢れる場にすることです。イメージとして、行政対市民みたいな敵対関係を感じている方は多いと思います。でもそれは違うと思うんです。市民にとって行政は欠かせないし、もちろん逆も然り。お互いが連携し合うことが大事です。その当たり前をつくるためにも、まずは小さい単位で笑顔が溢れる場をつくり、それをどんどん広げていきたいですね。
振り返ってみると、子どもの頃は勉強嫌いだった私が、今では当たり前のように本を読んだり、SNS動画を見たりしながら勉強するようになりました。子どもの頃も、実は嫌いなのではなくて、興味がなかっただけかもしれません。
そもそも社会人になると、待ちの姿勢では誰も教えてくれません。自分から動かなければ、学ぶことすらできないのです。学生時代に抱いていた学びの価値観は大きく変わりましたね。
私自身は、偶然からの学びと、目的があっての学びが大体7:3の割合です。人との出会いから感化されて学びにつながることが多いですね。学び方も、複数人でアウトプットをしながら学んでいくのが効率的だと気づきました。話すことで理解も深まりますし、他者の価値観に触れることで自分一人では気づかなかった視点も得られます。私がつながりを大事にして、ブログでの発信を行っているのは、自分自身の学びを深める側面もあるかもしれません。
その挑戦は、私のように大人になってからでも遅くはありません。一歩踏み出してみれば、いつでも変わることができるんです。
私自身、新たな一歩を踏み出します。2023年2月から、地方公務員を辞めて、企業で働くことにしました。IT系の企業で、公務員の業務支援などを掲げる会社です。地方公務員の仕事に一切の不満はありませんが、これまで一般の企業を経験したことがないし、いつかは別の視点も持ってみたいと考えていました。ちょうど募集があったタイミングで思い切って挑戦を決めました。
私のこれまでのキャリアを振り返ったとき、対人支援の中で「ありがとう」を言ってもらえることに、やりがいを感じることが分かりました。次の会社ではカスタマーサクセスを担当しますが、自分が生き生きと楽しくできる仕事だと思います。また、この仕事で培った知識や経験は、次のステップにいっても必ず活かせるはずです。
転職をしても変わらず、私の目標は富田林市を良くすることです。仕事をする中で、もちろん全国的な視点が必要ですが、長期的な視点として、最終的には富田林市というフィールドに落とし込みたいなと考えています。そのためにもたくさんの経験を積んで、人と人とをつなげ、地域をよりよい場所にしていきたいです。
編集後記
編集:株式会社ドットライフ
ライティング:林 春花
人と人との「つながり」を意識して活動している納さん。自らの強みについて、自覚はないけれどもと前置きをしつつ、「人の懐に入り込む力」と語っていました。たとえば、初めて出会った人には、「ありがとうございます」とメールを送るなど、当たり前のことは徹底しているとのこと。その言葉通り、このインタビュー後、筆者のもとにもメッセージが届きました。こうした小さな気遣いが、人と人とをつなげるコツなのだなと実感しました。公務員を辞めて新しい挑戦をする納さんが、これからどんな人と人とをつなげ、新しい価値を生み出していくのか楽しみです。
2022年12月21日取材
【新しい時代のWell-being】記事一覧
-
■
本当の自分の心を見つめ、誰もが幸せを感じられる社会に
ライフコーチ 佐伯 早織 -
■
社会への貢献は存在証明|見失ったアイデンティティを取り戻し生きる意味を見つけるまで
Plusbase inc. 創業者 / 看護師 ウィム・サクラ -
■
リサイクル率日本一の町で見つけた私の活躍場所|自ら見聞きした環境・地域の「リアル」がキャリアのヒントに
合作株式会社 地域連携事業部 ディレクター 藤田 香澄 -
■
ラップで心の病について発信し、社会の誤解をなくす
豊郷病院 精神科 作業療法士 佐々木 慎 -
■
中学校の地域学習から始まった。地元・伊豆での「幸せ」探し
伊豆市役所職員 飯塚 拓也 -
■
技能五輪全国大会・国際大会(世界大会)で活躍!周囲の協力を力に、自身の理想の姿へ向かっていく
日産自動車株式会社 事業投資部門 下原 侑也 -
■
エンジニアから新規事業開発へ 社内外との共創プロジェクトで価値を生み出す
日揮ホールディングス株式会社 サステナビリティ協創部 田中 悠太 -
■
理由なき大学進学に疑問を持ち、飛び出た日本 カナダで数学教師になり、生徒が主体となる授業を目指す
カナダの公立高校数学教員 梅木 卓也 -
■
「留職」で出会った私の使命 研究職から転向し、ビジネスで社会課題解決に挑む
日本電気株式会社(NEC) ビジネスデザイン職 松葉 明日華 -
■
「創薬」という大きな目標を追い求めながらも 日々の成長を大切に、一歩を積み重ねていく
大手製薬会社勤務 Bさん -
■
「誰かのために書く」を胸に単身パリへ ビジネスパーソンと書家であり続ける自分だけの道
アクセンチュア株式会社 書家 小杉 卓 -
■
誰も着手していない社会課題に信念を持って取り組んでいくことが自分の想いを世界にひろげる
株式会社manma 創業者 新居 日南恵 -
■
予測できない未来を選ぶ 釜石で課題に挑み続けた9年間
青森大学社会学部 准教授 石井 重成 -
■
周囲の人々を巻き込みながら多くの人に「楽しい」を届けたい
株式会社マンガボックス エンジニア こうたけ りな -
■
知らないことに出会う喜びを感じながら、人と人とを繋いで社会課題の解決を促進したい
株式会社STYZ ファンドレイザー/一般社団法人Earth Company ファンドレイザー/一般社団法人ELAB 理事 繋 奏太郎 -
■
自分の選択に自信と責任を持ち、女性として着実に成長できる場所を選ぶ
大手金融会社 Aさん -
■
「自分の幸せは何か」に向き合い 自分が誰を笑顔にしたいかを考え抜く
一般社団法人 歓迎プロデュース 理事 根岸 えま -
■
自分の好奇心を大切にしながら社会貢献をしていきたい
外資系大手IT企業 エンジニア 河村 聡一郎 -
■
どんなに小さな一歩でも、動き出すことが自分の世界を広げ、ほんの少しでも世界に影響をあたえる
軽井沢風越学園 教員 根岸 加奈 -
■
「選んだ道を正解にする」自分を信じて進路を選択し、事業を生み出す
株式会社ABABA(アババ) 代表取締役 久保 駿貴


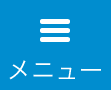
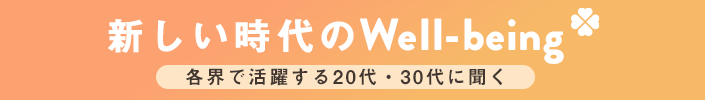

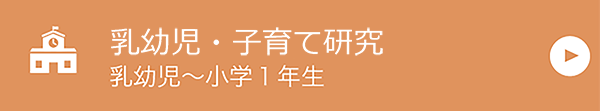
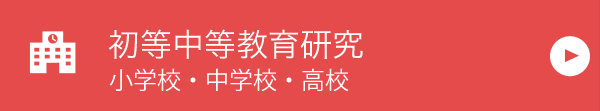

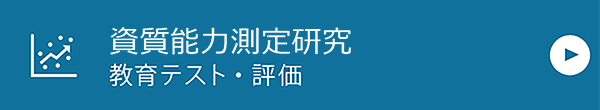
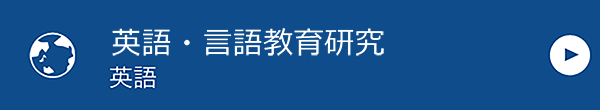
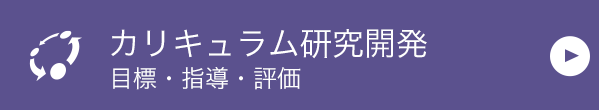
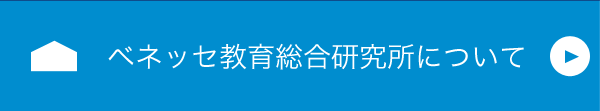
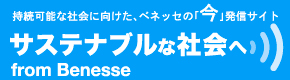
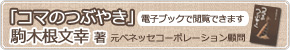
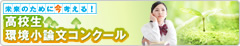
![ベネッセ教育総合研究所[公式ツイッター]](/images_sp/btn/btn_tw.png)