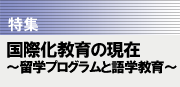 |
 |
 |
留学プログラムの増加と高校生・保護者の意識
「かつて日本の大学は、留学を希望する学生に学力と経済力があれば、個人として留学することはいつでも可能という認識を持っており、教育の一環として海外留学プログラムを整備している大学はほとんどなかった。留学は限られたエリートのためのものという意識が根強かったことも一つの理由」と南山大学外国語学部の近藤祐一助教授は言う。
南山大学では、70年代から「認定留学」という制度で、留学先で修得した単位を認定し、4年間で卒業できるシステムが構築されていた。当時、こうした海外大学との単位互換制度を整備している大学はごく少数で、大半が自大学で4年間の科目履修を行うことにより、学部教育を修了させる体制を取っていた。そのため、学生は留学のために休学しなければならず、留学先で苦労して修得した単位も認定されないことが多かったという。
バブル期を境に、休暇を利用して海外旅行に出かける日本人が急増し始めると、社会全体に「誰でも海外に行ける、誰でも留学できる」という風潮が高まった。こうした社会の変化に伴い、受験生や保護者が語学教育や海外の教育制度に強い関心を持つようになると、大学側も新たな留学制度の構築や拡充をせざるを得ない状況になった。「当時は内的、つまり大学改革の一部としての自発的な体制づくりではなく、外的要因によってプログラムを立ち上げたところがほとんどだった」と近藤助教授。
近年、大学の中に国際競争原理という概念も台頭し、大学のミッションとして国際的な視野を育成する教育の重視を掲げ、私学を中心に留学のプログラムを拡充しようとする動きが顕著だ。留学先で修得した単位の認定をはじめ、カリキュラムに海外研修や短期留学を組み込む大学も増えてきた。学生の目的や学年に合わせ、プログラム内容も多様化している。
入試広報の側面からみても、留学プログラムは重要な要素となっている。最近では、どの大学案内を見ても、教育の国際性が謳われ、規模の大小に関わらず海外研修や留学プログラムの紹介が必ず掲載されている。今や、留学は日本の大学教育の中で必要最低条件となってきた感がある。
「ただし、保護者にも留学経験者が増え、高い学費という対価を考えれば、日本の大学より海外で学ばせたほうがよいのでは、と考える人も少なくない。学生自身、大学入学までに海外渡航経験を持つ者も多く、留学することに何の抵抗感も持たない時代になってきた。海外の情報が手軽に入手できるため、ランキングやレベルを含めた大学に関する知識を持つ保護者も多く、学生が学びたい分野も多様化している。プログラム設置にあたり、大学は慎重に提携先の大学を選択し、内容を考えるべきだ」(近藤助教授) |
|