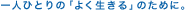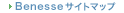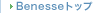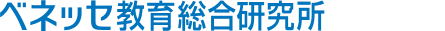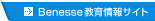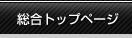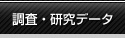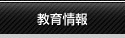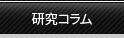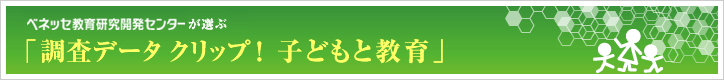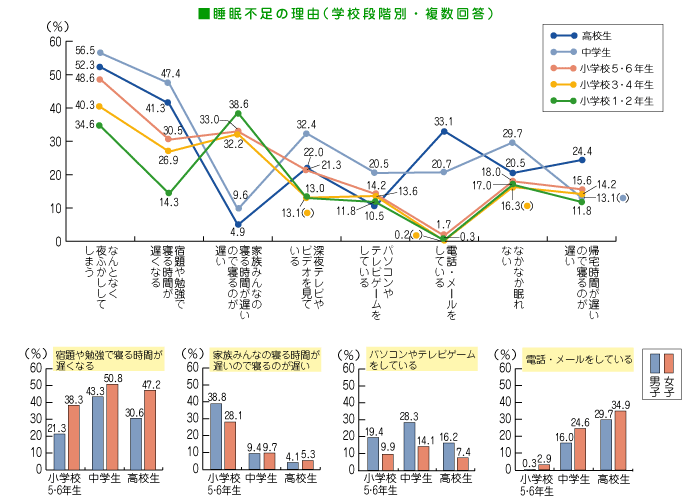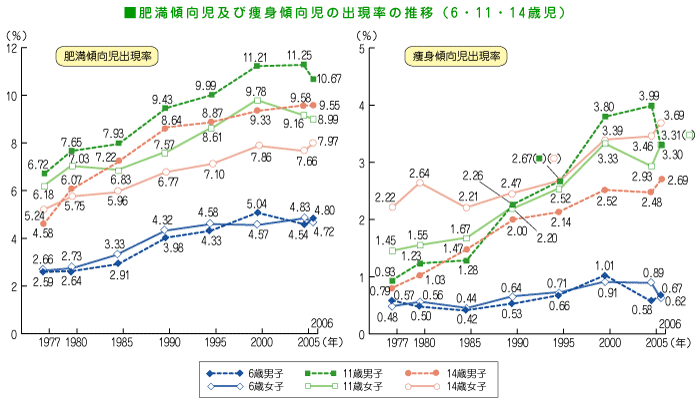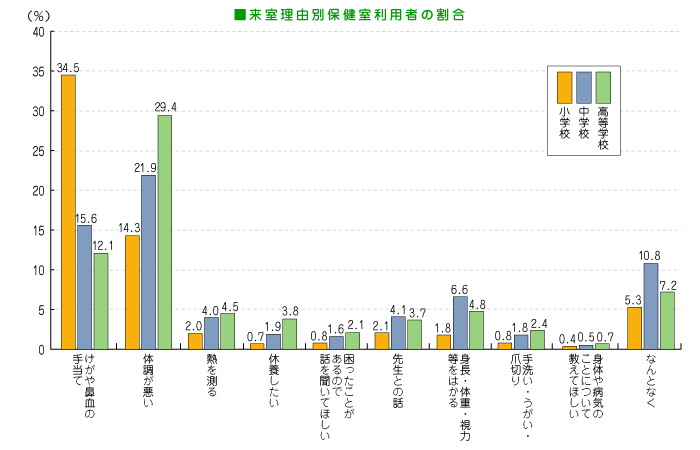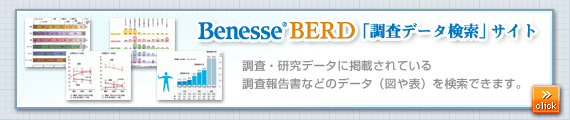���N �`��R��`
|
�y3-1�z�����s���̗��R�́u�Ȃ�ƂȂ���ӂ����v
- �o�T
- �u����18�N�x�������k�̌��N��ԃT�[�x�C�����X���ƕ��v���c�@�l���{�w�Z�ی���i2008�j
- �����Ώ�
- �S��13�s���̏��w�Z�A���w�Z�y�э����w�Z�v51�Z�i���w�� 5,134�l�A���w�� 2,450�l�A���Z�� 2,319�l�j
�������k�̐����s���̏ɂ��Ē��ׂ��������ʂ��݂�ƁA�u�ŋ߁A�����s���������Ă���v�Ɠ������������k�́A�S�̂Œj�q42.4���A���q51.8���ł���A�����߂��������s���������Ă��邱�Ƃ��킩�����B
�����s���������Ă��闝�R���݂Ă݂�ƁA�S�̂ł́u�Ȃ�ƂȂ���ӂ������Ă��܂��v�������Ƃ������A���w���A���Z���ł͔������Ă���B
�@ ���̑��̗��R���w�Z�i�K�ʂɂ݂Ă݂�ƁA���w�Z���E���w�N�ł́u�Ƒ��݂�Ȃ̐Q�鎞�Ԃ��x���̂ŐQ��̂��x���v�A�u�h�����ŐQ�鎞�Ԃ��x���Ȃ�v�Ƒ����B���w���ł́u�h�����ŐQ�鎞�Ԃ��x���Ȃ�v�A�u�[��e���r��r�f�I�����Ă���v�A���Z���ł́u�h�����ŐQ�鎞�Ԃ��x���Ȃ�v�A�u�d�b�E���[�������Ă���v�Ƒ����B
�h�����ȊO�̗��R�ł́A���w���͉Ƒ��Ƃ̉߂��������A�Q���Ԃɉe�����A���w���ȍ~�͉Ƒ��̉e�������Ȃ��Ȃ�A�e���r��r�f�I�A�d�b��[���Ƃ��������f�B�A�̉e�����Ă���l�q������������B�Ƃ��ɓd�b��[���Ƃ������R�~���j�P�[�V�����c�[���̉e���́A�w�Z�i�K�ƂƂ��ɑ傫���������Ă���B
�j���ʂɂ݂�ƁA�u�h�����ŐQ�鎞�Ԃ��x���Ȃ�v�A�u�d�b�E���[�������Ă���v�ł́A���q���j�q���������䗦�ƂȂ��Ă���A�u�p�\�R����e���r�Q�[�������Ă���v�ł́A�j�q�����q���������X���ɂ���B
�y3-2�z�얞�E���g�X�����Ƃ��ɒ����I�ɂ͑����X��
- �o�T
- �u�w�Z�ی����v�����v�����Ȋw�ȁi2007�j
- �����Ώ�
- ���w�Z�A���w�Z�A�����w�Z�A��������w�Z�y�їc�t���̎����A���k�y�їc��
�w�Z�ی����v�������A�U�E11�E14�Ύ��ɂ�����얞�X�����i�얞�x��20���ȏ�j�y�ё��g�X�����i�얞�x��-20���ȉ��j�̏o�����̐��ڂ��݂Ă݂�ƁA�얞�X�����A���g�X�����Ƃ��ɒ����I�ɂ͑����X���ɂ��邱�Ƃ��킩��B
�얞�X���̎q�ǂ��ɂ��Ă݂�ƁA14�Βj�q�ł́A1977�N��4.58������A2006�N��9.55���ƁA30�N�ԂŖ�Q�{�ɑ��������B14�Ώ��q�y�ё��̔N��ɂ����Ă��A�j���Ƃ���1.5�{����1.8�{�ɑ������Ă���B
�@ ����A���g�X���̎q�ǂ��́A�U�ł͒j���Ƃ��قډ����Ȃ̂ɑ��A11�Βj�q�ł�1977�N��0.93������2006�N��3.31����3.6�{�ɑ������A14�Βj�q�ł�3.4�{�A11�Ώ��q�ł�2.3�{�A14�Ώ��q�ł�1.7�{�ɂ��ꂼ�ꑝ�����Ă���B
�Ȃ��A2005�N����2006�N�ɂ����āA11�Βj�q���Ŕ얞�X�����E���g�X�����Ƃ��Ɍ����X�����݂���B2006�N�ȍ~�͔얞�Ƃ₹�̔������ύX�ƂȂ������߈�T�ɔ�r�ł��Ȃ����A2008�N�̓������i����j�ɂ��ƁA�e�N��Ŕ얞�X�����E���g�X�����Ƃ��Ɍ����X���ƂȂ����B�H��̐Z����A�Љ�I�Ƀ��^�{���f���̓����Ō��N�u�������܂������ƂȂǂ��A�e����^���Ă���Ɛ��������B
�y3-3�z�ی����������R�A�S�̌��N�ʂ̗��p������
- �o�T
- �u�ی������p�Ɋւ��钲�����i����18�N�x�������ʁj�v���c�@�l���{�w�Z�ی���i2008�j
- �����Ώ�
- ���w�Z�F373�Z�i202,284�l�j�A���w�Z�F369�Z�i183,852�l�j�A�����w�Z�F360�Z�i272,642�l�j
���w�Z�A���w�Z�A�����w�Z�ɂ�����ی����̗��p�𗈎����R�ʂɂ݂Ă݂�ƁA���w�Z�ł́u������@���̎蓖�āv��34.5���Ƃ����Ƃ������A���w�Z�ƍ����w�Z�ł́u�̒��������v�i���w�Z21.9���A�����w�Z29.4���j�������Ƃ������Ȃ��Ă���B
�@ ����A�u�Ȃ�ƂȂ��v�A�u�x�{�������v�A�u���������Ƃ�����̂Řb���Ăق����v�A�u�搶�Ƃ̘b�v�Ȃǂ̗��R�ŕی�����K��鎙�����k�����Ȃ��Ȃ��A�S�̌��N�ʂɂ����Ă��ی��������p����Ă��錻����������B
�@ �܂��A�O���t���������R�ȊO�ɂ��A�u�F�B�̂������E�t���Y���v�u���������v�u�ψ�����v���ł̗��p���������B
�������ɂ��ƁA�P�Z�P�����ς̕ی������p�Ґ��́A���w�Z40.9�l�A���w�Z37.9�l�A�����w�Z35.6�l�ł���A����13�N�����Ɣ�r����ƁA���w�Z��35.5�l����40.9�l�ƁA1.5�����������B���w�Z�A�����w�Z�͑傫�ȕω��݂͂��Ȃ��B�������R���݂�Ɓu������@���̎蓖�āv�����E���E���Ƃ��ɂQ���ȏ㑝�����A�܂��u�Ȃ�ƂȂ��v�ی����ɗ������Ă��钆�w���E���Z���������Ă���B
- �Q�l����
- �u����18�N�x�������k�̌��N��ԃT�[�x�C�����X���ƕ��v���c�@�l���{�w�Z�ی���
- �u�w�Z�ی����v�������v�����Ȋw��
- �u�ی������p�Ɋւ��钲�����i����18�N�x�������ʁj�v���c�@�l���{�w�Z�ی���