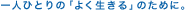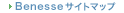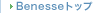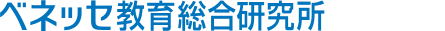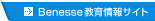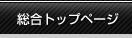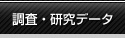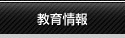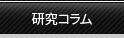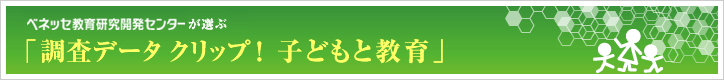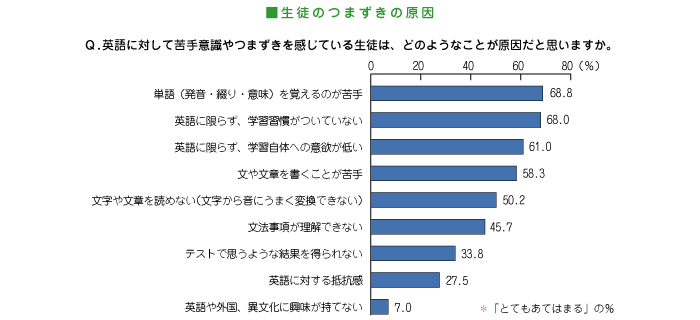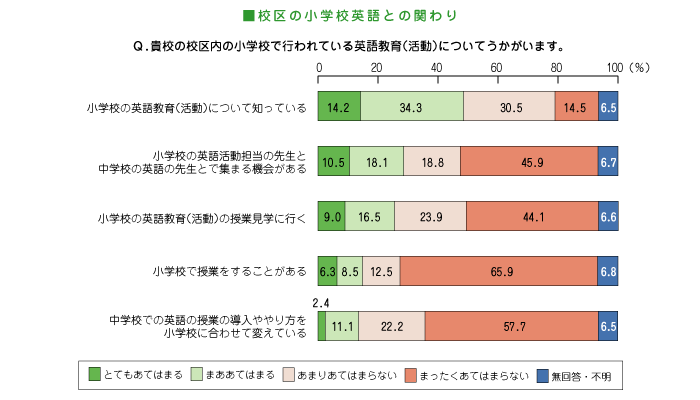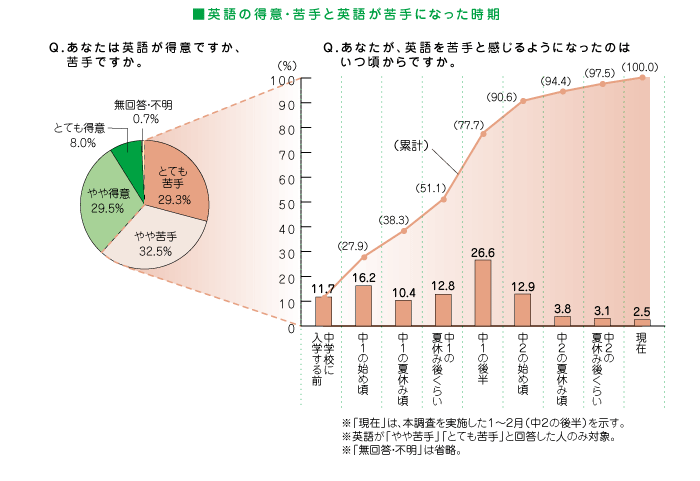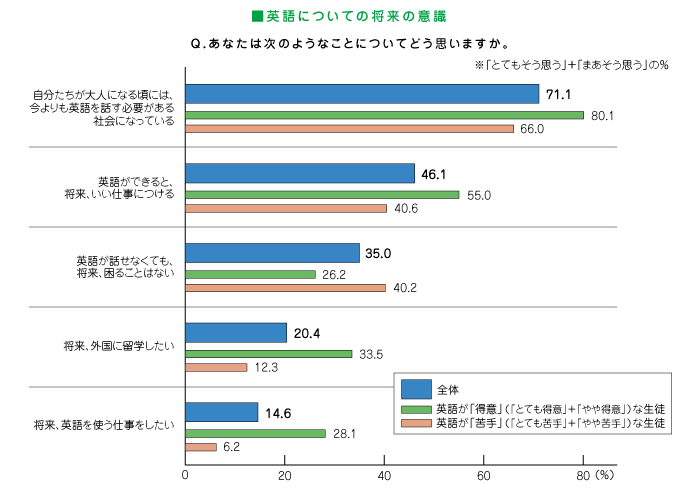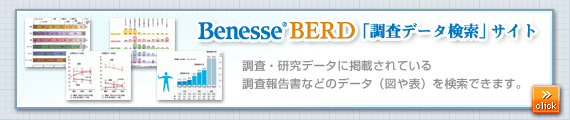�p�ꋳ�� �`��S��`
|
�y4-1�z�p��̂܂����̌������u�P��v�ƂƂ炦�鋳�����V��
- �o�T
- �u��P�w�Z�p��Ɋւ����{�����i���������j�@����Łv�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[�i2009�j
- �����Ώ�
- �S���̌������w�Z�̉p�ꋳ�� 3,643��
�S���̌������w�Z�̉p�ꋳ����ΏۂɁA���k�̉p��w�K�ɑ�����ӎ���܂����̎�Ȍ����������˂����ʂ��݂�ƁA�u�P��i�����E�Ԃ�E�Ӗ��j���o����̂����v��68.8���Ƃ����Ƃ������A��V���̋������A�p��w�K�ɑ��鐶�k�̂܂����̌����́A�P��̔�����Ԃ�E�Ӗ����o����Ƃ�������{�I�ȂƂ���ɂ���ƂƂ炦�Ă��邱�Ƃ��킩�����B
�������A�u�p��Ɍ��炸�A�w�K�K�������Ă��Ȃ��v�i68.0���j�A�u�p��Ɍ��炸�A�w�K���̂ւ̈ӗ~���Ⴂ�v�i61.0���j���U���ȏ�ƍ����A�p��w�K�Ɍ��炸�w�K�K�����̂ɑ傫�ȉۑ肪����ƔF�����Ă��鋳���������B
�p��̊w�K���e�Ɋւ�鍀�ڂł́A�u�P��i�����E�Ԃ�E�Ӗ��j���o����̂����v�Ɏ����ŁA�u���╶�͂��������Ƃ����v�i58.3���j�A�u�����╶�͂�ǂ߂Ȃ��i�������特�ɂ��܂��ϊ��ł��Ȃ��j�v�i50.2���j���T�����Ă���B
�@ ����u�p��ɑ����R���v��������������27.5���ƒႭ�A�u�p���O���A�ٕ����ɋ��������ĂȂ��v��7.0���ƂP���ɖ����Ȃ������B
�y4-2�z���w�Z�ł̉p�ꋳ��ɂ��āu�m���Ă���v�p�ꋳ���͔����ȉ�
- �o�T
- �u��P�w�Z�p��Ɋւ����{�����i���������j�@����Łv�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[�i2009�j
- �����Ώ�
- �S���̌������w�Z�̉p�ꋳ�� 3,643��
�S���̌������w�Z�̉p�ꋳ����ΏۂɁA�Z����̏��w�Z�ōs���Ă���p�ꋳ��i�����j�ɂ��Ă����˂����ʂ��݂�ƁA�u���w�Z�̉p�ꋳ��i�����j�ɂ��Ēm���Ă���v�Ɂu���Ă͂܂�i�ƂĂ����Ă͂܂�{�܂����Ă͂܂�̍��v�j�v�Ɖ��������́A48.5���Ɣ����ȉ��������B
�@����ɁA�Z����̏��w�Z�ōs���Ă���p�ꋳ��i�����j�Ƃ̊ւ��������˂��Ƃ���A�u���w�Z�̉p�ꊈ���S���̐搶�ƒ��w�Z�̉p��̐搶�ƂŏW�܂�@�����v��u���w�Z�̉p�ꋳ��i�����j�̎��ƌ��w�ɍs���v�Ɂu���Ă͂܂�v�Ɖ��������́A���ꂼ��28.6���A25.5���ƁA��������R���ɖ����Ȃ������B
�@�܂��A�u���w�Z�Ŏ��Ƃ����邱�Ƃ�����v�u���w�Z�ł̉p��̎��Ƃ̓�������������w�Z�ɍ��킹�ĕς��Ă���v�́A���ꂼ��14.8���A13.5���ƂP����ɂƂǂ܂��Ă���B
�{������2008�N�V�`�W���ɍs��ꂽ���̂ł��邪�A2011�N����̏��w�Z�ł̊O���ꊈ�����{�Ɍ����āA�����A�g������̉ۑ�Ƃ����邾�낤�B
�y4-3�z���w���̂U�����p��ɋ��ӎ��A�|�C���g�͒��P�㔼��
- �o�T
- �u��P�w�Z�p��Ɋւ����{�����i���k�����j�@����Łv�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[�i2009�j
- �����Ώ�
- �S���̒��w�Q�N�� 2,967��
�S���̌������w�Z�̒��w�Q�N����ΏۂɁA�p��̓��ӁE���ɂ��Ă����˂����ʂ��݂�ƁA�p��Ӂi�u�ƂĂ����Ӂv+�u��⓾�Ӂv�j�Ɠ��������k�͂S����i37.5���j�ł���̂ɑ��A���i�u�ƂĂ����v+�u�����v�j�Ɠ��������k�͂U���i61.8���j�ƁA�u���v���u���Ӂv��傫���������B
����ɁA�u���v�Ɖ������k���A�p����u���v�Ɗ�����悤�ɂȂ����������݂Ă݂�ƁA�u���P�̌㔼�v��26.6���Ƃ����Ƃ������A�����Łu���P�̎n�ߍ��v16.2���A�u���Q�̎n�ߍ��v12.9���A�u���P�̉ċx�キ�炢�v12.8���Ƒ����B
�@ �����v�ł݂�ƁA�p��ɋ��ӎ��������k�̂W���߂����A�u���P�̌㔼�v�܂łɉp����u���v�Ɗ�����悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��킩��B
�y4-4�z���w���̂V�����A�����̉p��̕K�v����F��
- �o�T
- �u��P�w�Z�p��Ɋւ����{�����i���k�����j�@����Łv�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[�i2009�j
- �����Ώ�
- �S���̒��w�Q�N�� 2,967��
�S���̌������w�Z�̒��w�Q�N����ΏۂɁA�p��ɂ��Ă̏����̈ӎ��������˂����ʂ��݂�ƁA�V�����A�u������������l�ɂȂ鍠�ɂ́A�������p���b���K�v������v�Ɗ����Ă��邱�Ƃ��킩�����B���̈���ŁA�u�p�ꂪ�b���Ȃ��Ă��A�����A���邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ɗ����Ă��鐶�k��35.0������B
�@�܂��A�u�����A�O���ɗ��w�������v�Ǝv�����k��20.4���A�u�����A�p����g���d�����������v�Ǝv�����k��14.6���ɂƂǂ܂��Ă���A�����A�p��̕K�v�������܂��Ă����Ƃ����F���������Ȃ�����A�������g���ϋɓI�ɉp����g�����Ƃ��C���[�W���Ă��鐶�k�͏��Ȃ����Ƃ��킩��B
����ɁA�e���ڂɂ��āA�p�ꂪ�u���Ӂv�Ȑ��k�Ɓu���v�Ȑ��k�ɕ����Ă݂Ă݂�ƁA���ꂼ��̍��ڂɂ�����14�|�C���g�`22�|�C���g�̊J�����݂�ꂽ�B
- �Q�l����
- �u��P�w�Z�p��Ɋւ����{�����i���������j�@����Łv�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[
- �u��P�w�Z�p��Ɋւ����{�����i���k�����j�@����Łv�x�l�b�Z���猤���J���Z���^�[