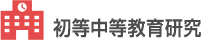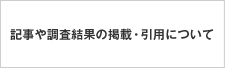報告書の概要
調査テーマ
学力格差発生のメカニズムを明らかにすること。
学力格差是正方策を提言すること。
調査方法
児童調査:学校通しによる自記式質問紙調査および学力調査(テスト)
保護者調査:学校通しによる家庭での自記式質問紙調査
担任の先生調査・校長先生調査:学校通しによる自記式質問紙調査
調査時期
第1期(19校):2007年11月15日~11月30日
第2期( 5校):2007年12月 3日~2008年 2月 1日
第3期(20校):2008年 1月25日~ 2月21日
調査対象
全国の 3地域(大都市圏、地方都市、郡部)の
(1)公立小学校 5年生の児童2,952名(配布数3,033通、回収率97.3%)
※児童回収数は、アンケート調査および算数学力調査で2,952通、国語学力調査では2,950通であった。
(2)その保護者2,744名(配布数3,033通、回収率90.5%)
(3)児童の担任の先生96名(配布数97通、回収率99.0%)
(4)児童の学校の校長先生44名(配布数44通、回収率100.0%)
調査項目
(1)児童調査:【質問紙調査】家での勉強日数(週当たり)/学校外学習/平日の行動時間/など。 【国語学力調査】現行の学習指導要領に示されている前学年までの目標が達成されているかどうかを確認する内容。 【算数学力調査】現行の学習指導要領に示されている前学年までの目標が達成されているかどうかを確認する内容。
(2)保護者調査:子どもへの接し方/親子での活動/学校外教育費/など
(3)担任の先生調査:授業の進め方/宿題について/評価について/など
(4)校長先生調査:教員の勤務年数/地域の特徴/学級編成基準/など
調査報告書の目次・詳細
| 調査研究の概要(耳塚寛明)、調査実施概要、 基本属性、学力調査問題解説(冨士原紀絵) |
|
||
| 基礎データ編
A.学力調査結果概要 |
|
||
| 分析編 第1章 学力の地域格差 大阪大学大学院教授 志水宏吉 |
|
||
| 第2章 家庭での環境・生活と子どもの学力 お茶の水女子大学大学院准教授 浜野 隆 |
|
||
| 第3章 階層差を克服する学校効果 ─「効果のある学校」論からの分析─ 大阪大学大学院教授 志水宏吉 |
|
||
| 第4章 格差を縮小する「学級効果」の探求 ─マルチレベルモデルを用いた分析─ 大阪大学大学院准教授 山田哲也 |
|
||
| 第5章 「言語による自己表現」が得意だと感じている子どもは誰か? ─家庭環境・学力・学校生活との関連を中心に─ 東京学芸大学准教授 金子真理子 |
|
||
| 第6章 学力調査の思想史的文脈 ─新しい国家統制か、それとも福祉国家の再定義か─ 東京大学大学院教授 小玉重夫 |
|
||
| 学力格差研究の課題 まとめにかえて お茶の水女子大学大学院教授 耳塚寛明 |
|
||
| 資料編 調査票見本(算数学力調査)、調査票見本(国語学力調査) |
|
||
| 基礎集計表(算数学力調査得点)、基礎集計表(国語学力調査得点)、 基礎集計表(児童アンケート) |
|
||
| 基礎集計表(保護者アンケート)、 基礎集計表(担任の先生アンケート)、 基礎集計表(校長先生アンケート) |
|
||
| 企画・分析メンバー |
|
分析検討会
|
学力格差調査から見えてきた実践課題 「教育格差の発生・解消に関する調査研究」の最後の分析検討会として、2008年12月27日(土)に研究メンバーが行った討論の様子をご紹介します。 |
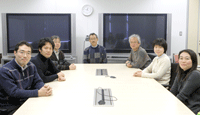 |