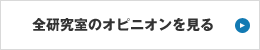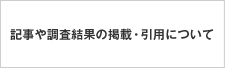多様化・グローバル化・デジタル化社会における教育課題に対する処方箋と直言をお届けします。
2018年
-

-
≫第126回 教育改革を実現するうえでこれから必要になること 『朝日新聞』との共同調査
(学校教育に対する保護者の意識調査)の結果をもとに考えるベネッセ教育総合研究所 主席研究員 木村 治生
2018.04.05
2017年
-

-
≫第121回 一生学び続けるを科学する⑱
「勉強が将来のために役に立つ」と思うことは自主的な学びにつながるのか特任研究員 太田 昌志
2017.02.16
-

-
≫第120回「一生学び続ける」を科学する⑰
小・中・高校生の自ら学ぶ力を獲得するプロセスを明らかにする
~家庭、学校・教員、社会の関わり方~主任研究員 邵 勤風
2017.02.02
2016年
-

-
≫第102回「一生学び続ける」を科学する① ~ベネッセ教育総合研究所が実践する研究概要~
ベネッセ教育総合研究所 副所長 小泉和義
2016.06.28
-

-
≫第101回 「学習基本調査」の結果を教育現場はどう読み解くのか ~「学ぶ意味と主体性」シンポジウムからみえてきた課題~
研究員 吉本 真代
2016.04.22
-

-
≫第100回 教員が「学びの改革」の担い手となるために -多忙な教員の声から学校教育の課題を考える-
研究員 木村 聡
2016.03.31
-

-
≫第98回 子どもたちが将来の目標を持てるよう促すには -「子どもの生活と学びに関する親子調査2015」の結果から-
研究員 橋本 尚美
2016.03.24
-

-
≫第94回 21世紀の子どもたちの育ちと学びを 科学する「子どもの生活と学び」研究プロジェクト ―大型パネル調査にかける思い
ベネッセ教育総合研究所 副所長 木村 治生
2016.02.23
-

-
≫第88回 「主体的な進路選択」に必要なこと
~「高校生活と進路に関する調査」結果から~主任研究員 邵 勤風
2016.01.14