格差構造の中で子どもの意欲を育むために
ベネッセ教育総合研究所 岡部悟志

家庭が子どもの学力を規定する
全国学力・学習状況調査から導かれた知見の1つに、子どもの学力の違いを説明する最大の要因は、学校や自治体の違いではなく、個々の子どもとその家庭レベルの違いだというものがある。具体的に数字をあげると、学校や自治体の違いの影響は合わせても1割程度にとどまるが、それ以外の約9割は、個々の子どもとその家庭による要因が占める1)。なかでも、子どもが選択できない家庭の影響が強いことは、私がこれまで取り組んできた全国調査の分析経験に照らしても、違和感はない。子どものジェンダーや学習時間、居住地域は学力と比較的関連が強いことが知られているが、それらを考慮してもなお、家庭の豊かさを示すSES(Socio-Economic Status; 家庭の社会経済的背景)が恵まれている子どもほど、学力が高い傾向がある。
加えて近年では、私たちの日常生活を取り巻く環境変化が、それに拍車をかけている。記憶に新しい新型コロナウイルス感染拡大下の学校・家庭教育では、本来あったはずの子どもの学びが失われた。しかし、そのダメージは一律ではなく、恵まれない家庭の子どもの方が大きかったことが世界的に報告されている2)。平時とは異なる混乱時においては、脆弱性の高い家庭の子どもほど負のインパクトを受けやすい。
高まる格差容認意識
どんな家庭で生まれるのか、どんな特性を持って生まれてくるのかは、誰も自由に選べない。そのような状況下で、人々はどのような社会を望ましいと考えるだろうか。政治哲学者のロールズは、生まれもった特性や家庭環境、遺伝などの情報がない状態において、誰もが人生のリスクや不確実性を意識せざるを得ないこと、そこでは、自分を含む誰もが最も不利な状況に置かれる可能性があり、そのような立場に置かれた人を最優先で支援することが社会的に合理的な選択となるとした3)。ロールズはそれを正義と呼んだ。教育や医療・福祉などの公的な支援の背景には、そのような考え方がある。
以上の考え方に従えば、生まれた家庭環境が子どもの学力を左右する現実があるとしたら、私たちは真っ先にそれを放置してはならないと考え、困難な状況にある家庭の子どもへの支援を支持するはずだ。ところが、実際には、子どもを持つ保護者の格差への容認意識(家庭の所得格差による子どもの教育格差は「当然だ」「やむをえない」とした比率)は、2010年代に入って大きく上昇している4)。なぜ、このようなことが生じるのだろうか。
なくならない格差の背景
格差への容認意識が高まっていることの要因の1つとして、近年の格差、とりわけ家族や子どもをめぐる格差が当事者の外から見えにくいことがある。例えば、子どもの貧困やヤングケアラーの存在は、これまで埋もれていた格差・不平等の問題が指摘され、社会的に認知された代表例だ5)。保護者のもとに置かれた子どもの立場や事情、同居する家族の中に世話をする/される関係があるということは、当事者の外からは見えにくい。そのため、多くの人はその存在や深刻さを感じることなく、見過ごすことになる。
また、そのような格差の存在が明らかとなり社会的に認知されたとしても、格差が根本的に解消されない理由もある。当事者による自己差別だ。裕福な家庭で育ち学力や地位を得た人は、自分が努力したことが原因と考える傾向が強い。一方で、厳しい家庭で生まれ学力や地位を得られなかった場合、それが生まれによる差だったとしても、自分の努力の至らなさや能力の低さに原因を求めがちだ。その結果、がんばっても仕方がない、がんばるにもがんばれない状況に追いやられてしまう。このようにして、生まれの格差が当事者の中に閉じられたまま、自己完結的に回収されてしまうことになる6)。
格差構造の中での子どもの意欲
とはいえ、既に大方決まっていている格差構造の中で、子どもの意欲はただ規定されてしまうだけのものなのだろうか。いくつかの研究では、子どもは自身が置かれた生まれの環境にただ翻弄されるだけの存在ではないこと、そして、自分の生まれとは異なる仲間集団や社会関係でのやりとりを通して、一人の意志を持った主体(エージェント)として自己を模索しながら形成し、新たな環境に適応していく様子が示されている。
例えば、志田(2015)は、ひとり親家庭で育った子ども本人への聞きとり調査によって、子どもが主体としてどのように生き抜こうとしているのかを描き出している。そこでは、困難な環境に置かれた子どもが、家庭以外の人のかかわりや承認を得ることを通して自身の置かれた状況を相対化した上で理解し直していた。また、似たような境遇にある同世代との出会いを通して他者とつながり、前向きに生きていた7)。たとえ家庭環境に恵まれなくても、家庭以外の養育者や指導者との間に、幼少期のアタッチメントに代わる良好な関係を育むことができれば、不利な家庭環境の影響は緩和される。こうした「保護効果」と呼ばれる事象の背景には、生まれの家庭とは異なる新たな社会関係の再構築がある。そして、それが期待される生活や学びの場の代表例が、就学前であれば地域の保育園、就学以降であれば学校であろう。子どもが家族以外の新たな社会関係を構築していく上で、子どもが多くの時間を過ごす園や学校という場が果たす役割は極めて重要と考えられる。
子どもが自ら意欲を育むために
園や学校現場では、現在の子どもが社会に出る2030年時点の環境変化を見据えた資質・能力の育成が目指されている。また、コロナ禍を経て、園での保育活動や学校の授業でのICT活用が大きく前進した。家庭環境によらず、学校や園を通じて養育者・指導者との関係性はもちろん、有用な情報やツールにアクセスできる機会はこれまでよりも確実に広がっているように思う。また、学校の授業では、ICTを活用して協働的な学びをより豊かにするような取り組みも進みつつある。子どもの意欲や肯定感を育むために、園や学校がどのような役割・機能を果たしうるか、また、そのためにどんな条件整備が必要かの検討が求められる。
格差構造の中で子どもが大人になる発達成長プロセスを再構築していくためには、園や学校での生活や学びを単なる一時的な居場所(シェルター)に留めるのではなく、子どもの社会化のための経験の場として位置づけること、そして、その中で子ども自身が自律的な意欲8)、すなわち自分の意志で選びとり、自ら意欲をコントロールし動機付けられることが重要となる。子どもの意欲の発達のダイナミズムを、研究を通して丁寧に描き出し、発信していくことが私たちの使命だと思う。
- <注>
- 1) 中西啓喜, 2023, 「コロナ禍の学校臨時休業によるラーニング・ロスの実証的研究――令和3年度文部科学省全国学力・学習状況調査の分析から」『教育社会学研究』112: p77-96.
- 2) ラーニング・ロスに関するメタ分析の代表的な例は以下。Betthäuser, B.A., Bach-Mortensen, A.M. & Engzell, P., 2023, “A Systematic Review and Meta-analysis of the Evidence on Learning during the COVID-19 Pandemic,” Nature Human Behaviour, 7(3): 375-385.
- 3) 齋藤純一・田中将人, 2021, 『ジョン・ロールズ――社会正義の探究者』中公新書.
- 4) ベネッセ教育総合研究所・朝日新聞社共同調査, 2018, 『学校教育に対する保護者の意識調査』(ダイジェスト版), p14.
- 5) 阿部彩, 2008, 『子どもの貧困――日本の不公平を考える』岩波書店. 澁谷智子, 2018, 『ヤングケアラー――介護を担う子ども・若者の実現』中公新書.
- 6) 低SES出身の高校生が学習から逃避する(降りる)ことで自尊心を保っていることが示されている。苅谷剛彦, 2001, 「<自信>の構造――セルフ・エスティームと教育における不平等」『階層化日本と教育危機――不平等再生産から意欲格差社会へ』有信堂.
- 7) 志田未来, 2015, 「子どもが語るひとり親家庭――『承認』をめぐる語りに着目して」『教育社会学研究』96: 303-323.
- 8) 櫻井茂男, 2019, 『自ら学ぶ子ども――4つの心理的欲求を生かして学習意欲をはぐくむ』図書文化社.
プロフィール
岡部 悟志
ベネッセ教育総合研究所 主任研究員
おかべ さとし
専門は教育社会学、学力格差。東京工業大学大学院社会理工学研究科博士課程修了.博士(学術)。これまで高等教育や社会人領域の調査研究を担当。現在は、乳幼児から初等中等領域までの、子どもの発達や成長、学力格差、保護者の子どもへのかかわりや教育観、教員の学習指導や学校・自治体でのICT活用などに関する調査研究に取り組む。
https://berd.benesse.jp/aboutus/member.php#0202



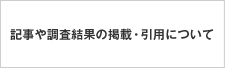






![ベネッセ教育総合研究所[公式ツイッター]](/images/index/ttl_twitter_mini.png)



